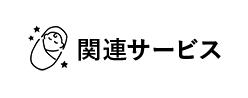期間限定キャンペーン中!
Contents
この記事を読んでいる人におすすめ!

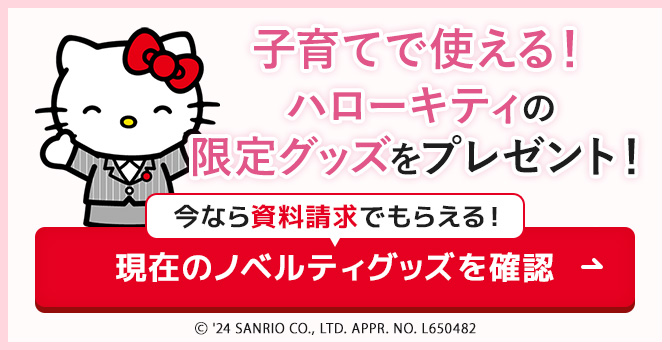
育休中にボーナスがもらえるかどうかは、勤務先の就業規則や給与体系などによって異なります。
この記事では、育休中にボーナスがもらえるケースともらえないケース、ボーナスにかかる社会保険料や税金、ボーナスがもらえなかった場合の対処法などについて詳しく解説しています。
※本記事の内容は公開日時点の情報となります。法令や情報などは更新されていることもありますので、最新情報を確かめていただくようお願いいたします。
そもそも育児休業とはどんな制度?
育児休業とは、原則として1歳未満の子どもを養育する労働者が取得できる休業制度です。労働者は育児・介護休業法にもとづいて育児休業を取得できる権利があり、会社側はこの申し出を拒否できません。育休期間中は給与が支払われないことが一般的ですが、育児休業等給付を受けられます。そのため、経済的な負担を軽減しながら育児に専念することが可能です。[参考1]
なお、育児休業は産休(産前産後休業)や育児休暇とは異なります。産休は出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から出産後8週間まで取得できる制度で、育児休業とは別に労働基準法で定められています。[参考2]
一方、育児休暇は企業独自の制度であり、法的な義務はなく、取得条件や期間は企業ごとに異なります。
これに対して育児休業は法律に基づく権利であるため、企業の規則に関わらず取得可能です。最近では、男性の育休取得も推奨されており、夫婦で協力して育児ができる環境づくりが進められています。
参考1:厚生労働省「育児休業の基本」
参考2:厚生労働省「産前・産後休業を取るときは」
育休中にボーナスはもらえる?

育休中にボーナスがもらえるかどうかは、就業規則や勤務していた期間によって異なります。ここでは、育休中にボーナスがもらえるケースと、もらえないまたは減額されるケースを見ていきましょう。
1.ボーナスがもらえるケース
就業規則や雇用契約書にボーナスに関する記載がある場合、育休中でもボーナスを含めた毎月の給与をを受け取れる可能性があります。特に査定期間中に勤務していれば、ボーナスを受け取れる可能性が高いです。
例えばボーナスが夏と冬の年2回支給される企業の場合、査定期間がそれぞれ「10月〜3月」「4月〜9月」などと設定されているのが一般的です。仮に4月から育休を開始していたとしても、10月から3月までの査定期間中に勤務していた実績があれば、夏のボーナスがもらえるかもしれません。
2.ボーナスがもらえない・ボーナスが減額されるケース
ボーナスの支給額は、企業の業績によって変動します。そのため、会社の業績が悪化するとボーナスがもらえなかったり、減額されたりするのです。
また、ボーナスの査定対象期間中に育休を取得していれば、ボーナスが不支給または減額される可能性があります。例えば査定期間が4月〜9月の場合に6月から育休を取得すると、対象期間における勤務実績が少なく、満額のボーナスを受け取れる可能性は低いでしょう。
3.年俸制の場合はボーナスがない
年俸制では年間の給与額があらかじめ決められており、その中にボーナスが含まれているケースが多いです。年間の給与を12分割して毎月の給与として支給する方式を採用しているため、そもそも夏や冬にボーナスは支給されません。
例えば年俸600万円で、毎月50万円(600万円 ÷ 12ヵ月)が支給されている場合は、別途ボーナスという形での支給はおこなわれないことが一般的です。そのため、年俸制の企業に在籍している場合は、育休中にボーナスを含めた毎月の給与を受け取れない可能性が高くなっています。
育休中にもらえるボーナスの社会保険料や税金はどうなる?
育休中にボーナスをもらったら、「社会保険料の支払いが必要かわからない」「課税されるのか知りたい」と疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。ここでは、育休中にもらったボーナスに対する社会保険料や税金について解説します。
1.社会保険料
ボーナスにかかる社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)は、一定の条件を満たした場合にのみ免除されます。同月内に14日以上にわたって育休を取得すると給与に対する社会保険料は免除されますが、ボーナスに対する社会保険料は必ずしも免除になるわけではありません。
ボーナスに対する社会保険料が免除されるのは、ボーナス支給月の末日を含んで1ヵ月を超える育休を取得している場合です。例えば7月にボーナスが支給される場合、7月31日を含んだ状態で1ヵ月以上の育休を取得していれば、ボーナスに対する社会保険料が免除されます。
一方で、7月1日から7月30日までのようにボーナス支給月の末日を含んでいない場合や、7月20日から8月15日までのように1ヵ月未満の育休の場合は、社会保険料が免除されません。[参考3]
参考3:厚生労働省・日本年金機構「育児休業等期間中の社会保険料免除要件が見直されます。」
2.雇用保険・所得税
雇用保険や所得税に関しては、ボーナスが給与の一部とみなされるため、通常通りに差し引かれます。雇用保険料は、ボーナスの支給額に対して雇用保険料率(2025年時点における一般事業の労働者負担は0.6%)をかけて求められます。[参考4]
例えば、ボーナスを50万円もらった場合の雇用保険料は3,000円(50万円×0.6%)です。雇用保険料はボーナスの金額に応じて決定されるため、ボーナスの支給額が高ければ負担額も増加します。
所得税の税率は課税所得額に応じて決まるため、ボーナスを受け取ることで所得税額が増加する可能性があります。年間の課税所得が194万9,000円以下の場合は所得税率が5%ですが、195万円以上329万9,000円以下の場合、10%になる仕組みです。そのため、ボーナスによって税率が変わる金額まで課税所得が増えると、所得税は高くなります。[参考5]
参考4:厚生労働省「令和6年度の雇用保険料率について」
参考5:国税庁「所得税の税率」
育休中にボーナスをもらえなかった場合の対処法
就業規則や労働契約書に支給条件が明確に定められている場合、条件を満たしていれば育休中でもボーナスを受け取れます。もし育休を理由に本来もらえるはずのボーナスが支給されなければ、雇用契約書や就業規則に育休中のボーナスについての取り扱いが明記されているかを確認しましょう。
ボーナスが支給されるはずにもかかわらず、受け取れなかったときは、使用者(会社側)と話し合ってください。それでも解決しない場合や、話し合いに応じてもらえない場合は、労働基準監督署に相談することも一つの方法です。労働基準監督署に相談すれば、企業に是正を求めるよう勧告してもらえるため、ボーナスを受け取れる可能性があります。[参考6]
参考6:宮城県公式ウェブサイト「賞与(ボーナス)がもらえないとき」
ボーナスをもらうと育児休業給付金が減ってしまうことはある?
育休中にボーナスをもらった場合でも、育児休業給付金が減ることはありません。育児休業給付金は、育児休業開始前の賃金日額を基準に算出されるためです。ボーナスは一時的な収入として扱われるため、育児休業給付金の算定基準には影響を与えません。[参考7]
なお育児休業給付金とは、育休中の生活を支援する目的で、一定の条件を満たした場合に雇用保険から支給される給付金です。[参考8]
育休開始から180日までの支給額は育休開始前の賃金日額の67%、それ以降は50%です。例えば休業前の賃金が月30万円の場合、最初の180日(約6ヵ月間)は20万1,000円(30万円 × 67%)、181日以降は15万円(30万円 × 50%)が支給されます。ボーナスはこの賃金日額には含まれません。[参考8]
育児休業給付金についてより詳しく知りたい方は「育休手当(育児休業給付金)とは?給付金額や期間、申請方法について徹底解説」もご覧ください。
参考7:厚生労働省「Q&A~育児休業給付~」Q12
参考8:厚生労働省「育児休業 、産後パパ育休や介護休業をする方を経済的に支援します」p.3,4
出産や育児で活用できる制度について紹介

出産や育児に関しては、経済的な負担を軽減するためにさまざまな制度が用意されています。これらの制度をうまく活用することで、育児にかかる費用を抑えたり、休業期間中の収入を確保したりすることが可能です。
新たな制度も導入されており、さらに育児と仕事を両立しやすくなっています。ここでは、出産や育児で活用できる制度を紹介します。
1.産後パパ育休(出生児育児休業)
2022年の改正で新たに導入された産後パパ育休は、子どもの出生後8週間以内に最大4週間取得できる育休制度です。原則として休業開始の2週間前までが申出期限ですが、通常の育休とは別で取得でき、出生直後の大切な時期に父親が積極的に育児に参加しやすくなっています。
産後パパ育休は2回に分けられるため、家庭の状況や母親の体調に応じて柔軟にスケジュールを調整できます。例えば子どもの出生直後に1週間取得し、その後1ヵ月後に再び3週間取得するといった方法も可能です。また、労使協定を締結している場合には、労働者が合意した範囲で休業期間中に就業することも認められています。[参考9]
なお、育児休業給付金と同様に一定の条件を満たせば、以下の式で算出される出生時育児休業給付金を受け取れます。
支給額 = 休業開始時賃金日額 × 休業期間の日数(28日が上限)× 67%[参考10]
参考9:厚生労働省「令和3(2021)年法改正のポイント」
参考10:厚生労働省「出生時育児休業給付金」p.4
2.出産手当金
出産手当金は、出産日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)と出産の翌日以降56日の間に、出産のために仕事を休んだ場合に健康保険から支給される給付金です。会社の健康保険に加入していて、出産前後に給与を受け取っていない、または給与が出産手当金の額よりも少ない場合に支給されます。また、退職後でも以下の条件を満たしていれば出産手当金を受け取ることが可能です。[参考11]
- 退職日まで継続して1年以上勤務し、健康保険に加入していた場合
- 出産手当金の対象期間(出産前42日+出産後56日)内に退職した場合
また休業1日ごとに、休業前にもらっていた給料(支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額)を30で割った金額の3分の2を出産手当金として受け取れます。例えば、休業前にもらっていた給料が月30万円とすると、30万円÷30日×(2/3)で、1日あたりの出産手当金は約6,666円となります。 [参考11]
参考11:全国健康保険協会「出産手当金について」
3.出産育児一時金
出産育児一時金は、出産にかかる費用を補助するために健康保険から支給される制度です。妊娠4ヵ月(85日)以上であれば、早産、死産、流産、人工妊娠中絶の場合も支給対象となります。[参考12]
2023年4月の制度改正により、支給額が42万円から50万円に引き上げられました。ただし、医療機関が産科医療補償制度に加入していない場合や、加入していても妊娠週数22週未満で出産した場合は48.8万円になります。[参考12]
また、健康保険組合から病院に出産育児一時金が支払われる直接支払制度を利用すれば、出産にともなう自己負担額を抑えられます。一方で、直接支払制度を利用しない場合は、出産費用を一時的に全額自己負担し、後から申請して支給を受けることも可能です。[参考12]
参考12:全国健康保険協会「子どもが生まれたときは出産育児一時金が受けられます。」
4.児童手当
児童手当は、0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもを養育している方に対して支給される制度です。子どもの成長にともなう経済的な負担の軽減が目的で、所得や子どもの人数に応じて支給額が決まります。
| 児童の年齢 | 児童手当の額(一人あたり月額) |
| 3歳未満 | 15,000円(第3子以降は30,000円) |
| 3歳以上高校生年代まで | 10,000円(第3子以降は30,000円) |
児童手当の支給時期は偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)で、それぞれの前月分までの2ヵ月分がまとめて支給される仕組みです。具体的には、6月の支給日には4月分・5月分の児童手当が振り込まれます。[参考13]
参考13:こども家庭庁「もっと子育て応援!児童手当」
まとめ
育休中にボーナスが支給されるかどうかは、勤務先の就業規則や労働契約によって異なります。もらえるか不安な場合は、就業規則にボーナスに関する記載がないか確認しておきましょう。
また、育休中にボーナスを受け取った場合でも、一定の条件を満たせば社会保険料の支払いは不要です。ただし所得税や雇用保険料は通常どおり控除されるため、手取り額が減る可能性があります。
育児・介護休業法の改正などによって、出産・育児に関する制度が充実してきています。出産手当金や育児休業給付金なども効果的に活用して、安心して育児に取り組める環境を整えましょう。
※本記事の内容は公開日時点の情報となります。法令や情報などは更新されていることもありますので、最新情報を確かめていただくようお願いいたします。
宮崎 千聖(みやざき ちさと)
FPライター。神戸大学経済学部卒業後、銀行の融資課にてローンの相談・手続きを担当した。退職後はライターとして、メガバンクや司法書士法人のオウンドメディアなどで記事を執筆。カードローンやクレジットカード、資産運用、債務整理など幅広いジャンルで執筆している。2級FP技能士、証券外務員一種
記事提供元:株式会社デジタルアイデンティティ