
期間限定キャンペーン中!
Contents
ボーナスは、企業が従業員に給与以外に支払われる特別な報酬です。しかし、ボーナスは社会保険料や税金などが控除されるので、企業から払われる金額と実際に従業員が受け取る手取り金額は異なります。
本記事では、ボーナスで控除される社会保険料や所得税の計算方法などを解説します。
※本記事の内容は公開日時点の情報となります。法令や情報などは更新されていることもありますので、最新情報を確かめていただくようお願いいたします。
ボーナスとは

ボーナスとは、毎月の給与とは別に企業が従業員へ支給する特別な報酬をいい、「賞与」や「特別手当」などとも呼ばれます。
給与と違い、ボーナスは法律上の支払い義務はありません。ボーナスの金額や回数、時期は各社の裁量に委ねられています。しかし、就業規則や労働協約等で定めていれば、企業はボーナスを支給しなければなりません。
法律では、賞与について以下のように定められています。[参考1]
| 所得税法第183条第2項に規定する賞与とは、定期の給与とは別に支払われる給与等で、賞与、ボーナス、夏期手当、年末手当、期末手当等の名目で支給されるものその他これらに類するものをいう。 |
参考1:国税庁「法第183条《源泉徴収義務》関係」
ボーナスは、一般的に夏・冬に支給されることが多いです。ボーナス支給額は、基本給連動型や業績連動型が多く、利益を還元する決算賞与などを支給している企業もあります。
ボーナスについて詳しく知りたい方は「ボーナス(賞与)はいつもらえるの?支給のタイミングや平均金額について」もご覧ください。
ボーナスから控除される税金や社会保険料
ボーナスは、会社から支給される金額の全額から社会保険料や税金が控除されます。
控除される社会保険料や税金にどのような種類があるのか、また控除金額の計算方法について、解説します。
1.社会保険料
賞与から控除されるものに、社会保険料があります。
以下では、控除される4つの保険料について解説します。
1.1.健康保険料
健康保険料は、病気やけがをした際にかかる医療費の自己負担を軽減するために支払う保険料です。会社員の場合、企業と本人が半分ずつ負担する仕組みになっています。
協会けんぽの場合、都道府県ごとに保険料率が異なります。
例えば東京支部の場合、令和7年度の健康保険料率は、介護保険第2被保険者に該当しない場合は9.91%、該当する場合は11.5%です。[参考2]
参考2:令和7年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表・健康保険料率
控除される健康保険料は、加入者および会社が折半して支払いますので、以下の計算式で算出します。
| 健康保険料=標準賞与額×健康保険料率÷2 |
標準賞与額とは、社会保険料などが控除される前のボーナス支給額の1,000円未満を切り捨てた金額です。
1.2.介護保険料
介護保険料とは、介護保険制度の運用に必要な費用をまかなうためのもので、40歳以上の国民が納める保険料です。ボーナスから控除される介護保険料も、健康保険料と同様に、企業と本人が半分ずつ負担します。
介護保険料率は毎年見直しが行われ、2025年度の介護保険料率は全国一律で1.59%です。[参考3]
介護保険料の計算式は、以下の通りです。
| 介護保険料=標準賞与額 × 保険料率 ÷2 |
参考3:全国健康保険協会「令和7年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます」
1.3.雇用保険料
雇用保険料は、失業したときや育児・介護休業を取得した際などに、給付金などの支援を受けるために必要な保険料で、雇用保険料もボーナスから差し引かれます。事業主と労働者がそれぞれ負担します。
労働者の雇用保険料率は業種によって異なります。
2025年度は、一般の事業は0.55%、農林水産・清酒製造事業・建設業は0.65%です。[参考4]
労働者が負担する雇用保険料は、以下の計算式で算出されます。
| 雇用保険料=標準賞与額×雇用保険料率 |
参考4:厚生労働省「事業主・被保険者の皆さまへ令和7(2025)年度 雇用保険料率のご案内」
1.4.厚生年金保険料
厚生年金とは、会社員や公務員として働く人が主に加入する公的年金制度です。
被保険者(会社員・公務員など)が払う厚生年金保険料は、以下の計算式より算出します。
| 厚生年金保険料=標準賞与額×厚生年金保険料率÷2 |
健康保険料同様、厚生年金保険料も被保険者および事業者(会社)が折半して支払います。
2025年4月現在、厚生年金保険料率は18.3%です。被保険者(会社員・公務員など)が控除されるのは半分の9.15%です。[参考5]
参考5:日本年金機構「厚生年金保険の保険料」
2.所得税
社会保険料同様、ボーナスから控除されるものに所得税があります。
所得税は、個人の所得に対してかかる税金です。ボーナスは給与同様、所得であるため、控除されます。
所得税額は、以下の算式により求められます。
| 所得税額=(標準賞与額-社会保険料等)×所得税率 |
注意すべき点として、所得税率は、標準賞与額に対してではなく、ボーナスが支給される前月の給与から、社会保険料を控除した金額に応じて所得税率(0%~45.945%)が決まります。[参考6]
給与金額以外にも、扶養親族の人数によっても税率が変わる点にも注意しましょう。
参考6:国税庁「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和7年分)」
ボーナスの手取り額のシミュレーション
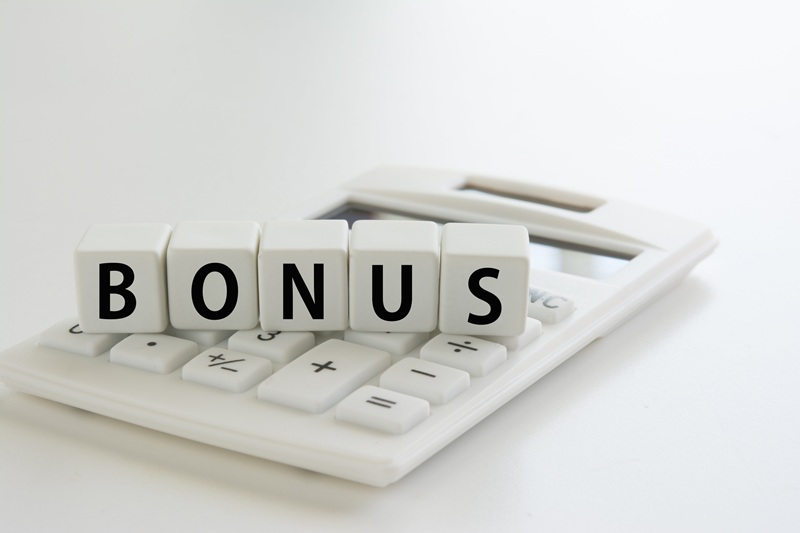
では、ボーナスの手取り額がいくらになるのかについて、以下の2つのシミュレーションを使って確認しましょう。
1.ボーナスが40万円の場合
以下の条件を想定して、ボーナスの手取り額を算出します。
【条件】
- 東京都在住
- 25歳
- 一般企業の会社員
- ボーナス支給の前月の給与(社会保険料控除後)20万円
- 協会けんぽ加入
- 扶養家族なし ・標準賞与額は40万円
控除される金額をそれぞれ計算します。
- 健康保険料+介護保険料:400,000円×9.91%÷2=19,820円
※25歳のため、介護保険料は0円 - 厚生年金保険料:400,000円×18.3%÷2=36,600円
- 雇用保険料:400,000円×0.55%=2,200円
よって、社会保険料合計は以下の通りです。
社会保険料合計:19,820円+36,600円+2,200円=58,620円
所得税額は、以下の計算式で算出します。
所得税額=(標準賞与額-社会保険料等)×所得税率
注意すべき点は、所得税率です。
社会保険料控除後のボーナス支給の前月の給与が20万円、扶養家族なしの条件では、賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和7年分)によれば4.084%です。
そのため、所得税額は以下のようになります。
所得税額:(400,000円-58,620円)×4.084%=13,941円(1円未満切り捨て)
よって、手取りのボーナスは以下の通りです。
400,000円-(58,620円+13,941円)=327,439円
2.ボーナスが60万円の場合
続いて、ボーナスが60万円の場合です。
以下の条件を想定して手取り金額を計算します。
【条件】
- 東京都在住(40歳)
- 一般企業の会社員
- ボーナス支給の前月の給与(社会保険料控除後)30万円
- 協会けんぽ加入
- 扶養家族1人
- 標準賞与額は60万円
控除される金額は以下の通りです。
- 健康保険料+介護保険料:600,000円×11.5%÷2=34,500円(1円未満切り捨て)
- 厚生年金保険料:600,000円×18.3%÷2=54,900円
- 雇用保険料:600,000円×0.55%=3,300円
ボーナスから控除される社会保険料の合計は以下の通りです。
社会保険料合計:34,500円+54,900円+3,300円=92,700円
続いて、所得税額を計算します。
先ほどの事例同様、条件より賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和7年分)から該当する利率を見つけます。
社会保険料控除後のボーナス支給の前月の給与が30万円、扶養家族1人の条件では、6.126%です。
所得税額は以下のようにして求めます。
所得税額:(600,000円-92,700円)×6.126%=31,077円(1円未満切り捨て)
よって、手取りのボーナスは、次の通りです。
600,000円-(92,700円+31,077円)=476,223円
ボーナスの平均はどれくらい?
厚生労働省が公表している「毎月勤労統計調査 令和7年2月分結果速報等」によると、2024年冬季賞与の事業所の1人あたりの平均額は41万3,277円で、前年から2.5%増えています。[参考7]
業種別では、以下の通りとなっています。
【令和6年年末賞与の支給状況】
| 業種(産業) | 労働者一人平均賞与額 | ||
| 令和6年 | 令和5年 | 前年比 | |
| 鉱業・採石業等 | 612,066円 | 581,210円 | 14.5 % |
| 建設業 | 540,595円 | 499,260円 | 8.0% |
| 製造業 | 558,186円 | 523,946円 | 5.6% |
| 電気・ガス業 | 943,474円 | 803,194円 | 13.5% |
| 情報通信業 | 707,303円 | 713,851円 | -2.2% |
| 運輸業・郵便業 | 398,540円 | 411,790円 | -2.1% |
| 卸売業・小売業 | 373,565円 | 367,165円 | 2.2% |
| 金融業・保険業 | 641,032円 | 645,024円 | -1.0% |
| 不動産・物品賃貸業 | 551,281円 | 548,808円 | 1.7% |
| 学術研究等 | 588,937円 | 630,490円 | -6.7% |
| 飲食サービス業等 | 83,199円 | 69,234円 | 12.1% |
| 生活関連サービス業等 | 184,277円 | 170,269円 | 9.4% |
| 教育・学習支援業 | 589,333円 | 535,395円 | 6.5% |
| 医療・福祉 | 308,846円 | 290,826円 | 8.8% |
| 複合サービス事業 | 455,496円 | 459,608円 | -0.1% |
| その他のサービス業 | 236,048円 | 239,074円 | 1.0% |
参考7:厚生労働省|毎月勤労統計調査 令和7年2月分結果速報等
まとめ
ボーナスは「賞与」「特別手当」などと呼ばれ、企業が支給する特別な報酬です。通常、ボーナスは企業から支給される金額から、社会保険料や所得税が控除されます。
扶養家族数や、前月の給与(社会保険料控除後の金額)により、ボーナスに適用される所得税率も変化します。
どれくらいの金額が控除されるのかについて把握しておくのも、資金計画を立てる場合にも有効といえるでしょう。
※本記事の内容は公開日時点の情報となります。法令や情報などは更新されていることもありますので、最新情報を確かめていただくようお願いいたします。
宮本 建一(みやもと けんいち)
マネーライター。銀行・消費者金融・信用組合の勤務を経て独立。融資経験・FPの知見を生かし、各種サイトで主に資金調達、不動産関連記事の執筆を行う。金融専門誌への寄稿、金融機関行職員向けの通信講座教材執筆経験あり。2級ファイナンシャルプランニング技能士、AFP、金融内部監査士
記事提供元:株式会社デジタルアイデンティティ








