
期間限定キャンペーン中!
Contents
「年収600万円あれば、暮らしに余裕があるはず」だと思っていたのに、毎月の生活にゆとりがないと感じている方もいるのではないでしょうか。税金や社会保険料などが差し引かれるため、600万円を自由に使えるわけではありません。
この記事では、年収600万円の人のおおまかな手取り額と、単身/3人家族それぞれのリアルな生活シミュレーションを公開しています。また、年収を増やすためにできることや、将来に備えるために効果的な方法も紹介します。
※本記事の内容は公開日時点の情報となります。法令や情報などは更新されていることもありますので、最新情報を確かめていただくようお願いいたします。
年収600万円の手取りはいくら?
年収とは、1年間に支払われる給与の総額で、毎月の給与に賞与(ボーナス)を加えたものです。額面は毎月の給与明細に記載される支給総額、手取りはそこから所得税・住民税・社会保険料などを差し引いた後に実際に受け取る金額です。
毎月の手取り額は扶養家族の有無やボーナスの有無、居住地域などによって変動しますが、一般的には額面給与の70%〜80%程度になるとされています。例えば、年収600万円の場合の手取り額は以下の通りです。
| 手取りの目安(年間) | 手取りの目安(月間) | |
| ボーナスなし | 600万円 × 70% = 約420万円 600万円 × 80% = 約480万円 | 約35万円〜約40万円 |
| ボーナスあり ※一例として100万円(年2回)とする | 通常月の手取り 約29.2万〜33.3万円 ボーナス月の手取り(年2回) 約64.2万〜73.3万円(月給手取り + ボーナス手取り) |
年収600万円の人の割合はどれくらい?
国税庁の令和5年分民間給与実態統計調査によると、民間の事業所に1年間勤務した給与所得者のうち、年収600万円台の人の割合は以下のようになっています。[参考1]
| 分類 | 年収600万円台の人の割合 |
| 男性 | 10.0% |
| 女性 | 3.4% |
| 男女全体 | 7.1% |
男女別で見ると男性は10.0%、女性は3.4%で、 年収600万円の割合は男性の方が高めです。
この背景には、依然として残る男女の賃金格差や、ライフイベントの影響が考えられます。特に女性の場合、出産や育児、介護といった家庭の事情を理由に、働き方を変えたり、キャリアの中断を余儀なくされたりするケースが少なくありません。また、非正規雇用の割合が男性より高いことも、女性の年収が上がりにくい要因の一つでしょう。
なお、全体の7.1%という数字を見ると、年収600万円台は決して珍しい水準ではないものの、実際にこの金額に届いている人はまだ限られていることがわかります。
参考1:国税庁「令和5年分民間給与実態統計調査-調査結果報告-」22ページ
【男女】【年齢】【業種】別でみた平均年収
年収600万円という水準が、世の中でどの程度の位置にあるのかをより具体的に把握するには、性別・年齢・業種ごとの平均年収と比較することが有効です。ここでは、令和5年分民間給与実態統計調査(非正規雇用含む)のデータをもとに、分類ごとの平均年収を確認していきます。
1.【男女別】平均年収

男性と女性では、平均年収(平均給与)に大きな差があります。ここでは、男女それぞれの平均年収(平均給与)について、詳しく見ていきましょう。
| 性別 | 平均給与 |
| 男性 | 約5,685,000円 |
| 女性 | 約3,158,000円 |
男性の平均年収(平均給与)は約570万円と、600万円に近い水準まで到達していますが、女性の平均年収(平均給与)は約320万円と大きく下回っています。
これは、結婚・出産・育児などにより非正規雇用や短時間勤務を選ぶ女性が多いこと、女性の管理職・専門職への登用が進んでいないことなどが影響しているでしょう。年収600万円は、男女間で見ると男性では平均以上、女性では平均よりかなり上の高収入層といえます。
参考2:国税庁「令和5年分民間給与実態統計調査-調査結果報告-」16ページ
2.【年齢別】平均年収
年齢別に見ると、40代〜50代の平均年収(平均給与)が高くなっています。ここでは、年代ごとの平均年収(平均給与)について、チェックしてみましょう。
| 年齢 | 平均給与 |
| 19歳以下 | 約112万円 |
| 20歳〜24歳 | 約267万円 |
| 25歳〜29歳 | 約394万円 |
| 30歳〜34歳 | 約431万円 |
| 35歳〜39歳 | 約466万円 |
| 40歳〜44歳 | 約501万円 |
| 45歳〜49歳 | 約521万円 |
| 50歳〜54歳 | 約540万円 |
| 55歳〜59歳 | 約545万円 |
| 60歳〜64歳 | 約445万円 |
| 65歳〜69歳 | 約354万円 |
| 70歳以上 | 約293万円 |
30代では400万円台が中心で、年収600万円は40代後半〜50代の平均を超える水準(非正規雇用を含む)です。つまり、年収600万円は経験やスキルを重ねた結果として得られる水準であり、20代〜30代のうちに達成していれば、かなり高収入といえるでしょう。
参考3:国税庁「令和5年分民間給与実態統計調査-調査結果報告-」20ページ
3.【業種別】平均年収
業種別に見ても平均年収(平均給与)には大きな差があります。ここでは業種ごとに、平均年収(平均給与)を見ていきましょう。
| 業種 | 平均給与 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 約775万円 |
| 金融業・保険業 | 約652万円 |
| 情報通信業 | 約649万円 |
| 学術研究・専門・技術サービス業・ 教育・学習支援業 | 約551万円 |
| 建設業 | 約548万円 |
| 複合サービス事業 | 約535万円 |
| 製造業 | 約533万円 |
| 運輸業・郵便業 | 約473万円 |
| 不動産業・物品賃貸業 | 約469万円 |
| 医療・福祉 | 約404万円 |
| 卸売業・小売業 | 約387万円 |
| サービス業 | 約378万円 |
| 農林水産・鉱業 | 約333万円 |
| 宿泊業・飲食サービス業 | 約264万円 |
| 全体平均 | 約460万円 |
年収600万円は、全体平均(460万円)を大きく上回る水準であり、どの業種でも到達できるとは限りません。特に高水準となっているのは、電気・ガス・熱供給・水道業(775万円)といったインフラ系や、金融・保険業(652万円)、情報通信業(649万円)といった専門性の高い分野です。
これらの業界は、大手企業が多く安定性も高いため、給与水準も比較的高くなりやすい傾向があります。また、職種によっては国家資格や高度なITスキルなどが求められ、能力や経験によって収入が伸びやすいという特徴もあります。
一方で、宿泊業・飲食サービス業(264万円)やサービス業(378万円)などの対人接客が中心の業種では、平均年収は低めです。これは、非正規雇用やパートタイムで働く人の比率が高いことに加え、労働集約型のビジネスモデルが多く、利益率が低い構造であることも影響しているでしょう。
参考4:国税庁「令和5年分民間給与実態統計調査-調査結果報告-」19ページ
給与から差し引かれる税金や社会保険料について
給与から税金や社会保険料などが差し引かれた金額が振り込まれているため、振り込まれた給与を見て「思ったより手取りが少ない」と感じたことがある方も多いのではないでしょうか。ここでは、各項目の内容や、差し引かれる金額の目安を解説します。
1.所得税・住民税
所得税は国に納める税金で、主に社会保障や公共サービスの財源として活用されています。例えば年収600万円で控除額が合計300万円だった場合、課税所得は300万円となり、この金額に対して所得税がかかる仕組みです。
所得税の控除には、給与所得控除や基礎控除、配偶者控除、扶養控除などさまざまな種類があり、家族構成や働き方によって適用内容が異なります。また、所得税は「累進課税制度」が採用されており、課税所得が多くなるほど税率が高くなります。
税率は5%〜45%まで段階的に設定されており、年収600万の場合は、10%〜20%の税率が適用されるのが一般的でしょう。 [参考5]
また、住民税はお住まいの自治体に支払う地方税で、教育や福祉、地域インフラの整備などに充てられます。住民税の納税額は、課税所得に対して10%の「所得割」に5,000円程度の「均等割」を加えた金額です。
参考5:国税庁「所得税の税率」
2.健康保険料・介護保険料
健康保険料は、医療費の自己負担を軽減するための制度に使われるもので、会社員の場合は企業と折半で支払います。協会けんぽに入っている方の場合、保険料は、標準報酬月額(4月〜6月の給与の平均)に協会けんぽが定める保険料率をかけると求められます。
年収600万円(月収50万円)で、標準報酬月額が50万円の等級と仮定した場合、健康保険料の自己負担は、月24,775円、年29万7,300円です。[参考6]
さらに、40歳以上になると介護保険料の支払いも加わります。東京都の介護保険料率で計算すると、月3,975円程度・年間で47,700円が上乗せされます。[参考6]
健康保険料は加入している組合によって異なることがあります。また、協会けんぽの場合、健康保険料と介護保険料は、年収だけでなく年齢や居住地によっても変動します。
参考6:全国健康保険協会「令和7年度保険料額表(令和7年3月分から)東京支部」
3.厚生年金保険料
厚生年金保険料は、将来の老後資金や障害・遺族年金などの財源となる重要な保険料です。会社員として働く場合、原則として厚生年金に加入し、保険料は会社と本人が折半で支払います。
保険料は標準報酬月額に、厚生年金の保険料率9.15%をかけて計算されます。例えば、年収600万円で標準報酬月額が50万円であれば、厚生年金保険料の負担は年45,750円、年間54万9,000円です。なお、同額を勤務先も負担しており、実際の保険料総額はその倍額になります。[参考7]
参考7:日本年金機構「厚生年金保険料額表」
4.雇用保険料
雇用保険料は、失業した際の基本手当や、育児・介護休業中の給付金などの財源となる社会保険料です。会社員であれば原則として加入が義務づけられており、企業と従業員が保険料をそれぞれ負担する仕組みです。2025年度(令和7年度)の一般事業における労働者負担分の保険料率は、0.55%に設定されています。[参考8]
よって、年収600万で月収が50万円の場合の一般事業における労働者の雇用保険料は、月2,750円、年間33,000円になります。
参考8:厚生労働省「令和7(2025)年度 雇用保険料率のご案内」
年収600万円の生活レベルはどれくらい?
年収600万円と聞くと、ある程度ゆとりのある生活ができそうに思えますが、実際には税金や社会保険料が差し引かれるため、可処分所得はそれほど多くありません。
ここでは、総支給額の75%である月37.5万円を手取りと仮定し、単身世帯と3人家族(夫婦+子ども1人)のケースで生活シミュレーションを行ってみましょう。消費支出は総務省の「2023年度 家計調査(家計収支編)」の金額を引用します。
1.単身の場合
総務省「2023年度 家計調査年報(単身世帯)」によると、単身勤労者世帯の1ヵ月あたりの平均消費支出は約16万9,547円です。これに対して、月の手取りが37.5万円あれば、毎月の黒字はおよそ20万円強と、かなりの余裕がある生活が可能です。[参考9]
ただし、この統計には実家暮らしや持ち家で家賃がかからないケースも含まれており、家賃の平均は約23,000円に留まっています。一人暮らしをする場合、家賃を2万円台に抑えることは難しいため、実際には毎月の黒字は少なくなります。しかし、節約や資産形成をしやすい水準であることに変わりはないでしょう。
参考9:e-Stat「家計調査年報(家計収支編)令和5年単身世帯」表番号1 1世帯当たり1か月間の収入と支出 単身世帯
2.3人家族の場合
総務省「2023年度 家計調査(二人以上の世帯)」によれば、夫のみ有業・妻と子ども1人の世帯の平均消費支出は月30万5,727円です。月の手取りが37.5万円と仮定すると、支出との差額は約7万円弱です。一見すると余裕があるように見えますが、実際はそう単純ではありません。[参考10]
この平均支出には、持ち家や社宅などで家賃負担が少ない世帯も含まれており、住居費は約23,000円に抑えられています。しかし、仮に家賃が10万円だとすれば、生活費全体は40万円を超え、手取り37.5万円では赤字に転じてしまいます。
さらに、子どもの成長にともなって教育費や食費が増えることを考えると、毎月の黒字だけでは将来の出費に備えにくい状況です。そのため、3人家族で安定した暮らしを続けていくには、節約や支出の見直しに加え、共働きや副業による収入増加が必要になるでしょう。
参考10: e-Stat「家計調査年報(家計収支編)令和5年家計収支編 二人以上の世帯」詳細結果表 夫のみ有業のうち夫婦と未婚の子供1人の世帯
年収をもっと増やすためにできること
年収600万円は決して低くはありませんが、家族構成や居住地によっては「思ったより余裕がない」と感じることもあります。今後のライフイベントや老後を見据えるなら、収入をさらに伸ばす選択肢を検討することが大切です。
ここでは、年収アップに向けた具体的なアプローチを紹介します。
1.スキルアップや資格を取得する
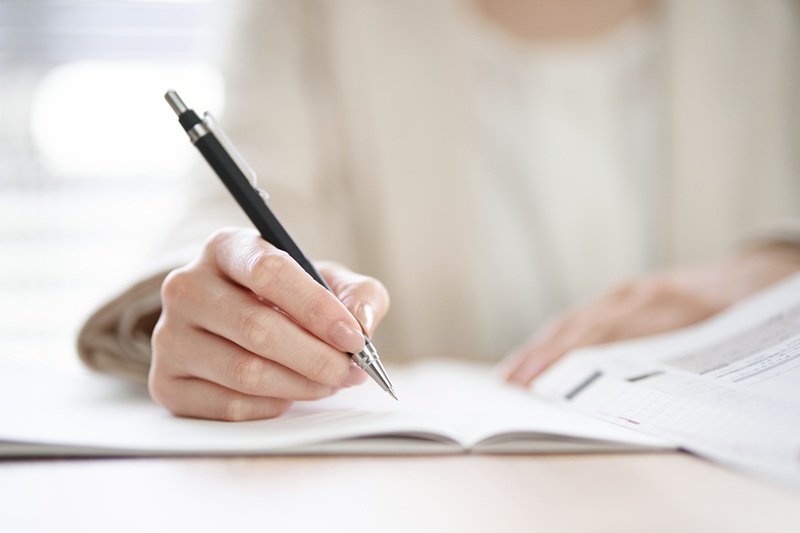
スキルアップや資格取得によって自身の市場価値を高めることで、年収アップを目指せます。例えば、マネジメント力や営業力、広告運用スキル、データ分析力といった実務に直結するスキルは、日々の業務で成果を出すうえでも、社内評価を高めるうえでも重要です。スキルのある人材は責任あるポジションを任されやすく、昇進や昇給にもつながりやすくなります。
そして、スキルは自社内で評価されるだけでなく、転職時の武器にもなります。たとえ今の職場で大きな昇給が望めないとしても、スキルの蓄積があれば、より条件のよい企業へステップアップすることが可能です。
また、資格取得も年収アップに役立ちます。企業によっては資格手当が支給されるほか、昇格や管理職登用の条件として資格が求められるケースもあります。宅地建物取引士(不動産・営業職向け)や基本情報技術者(IT・システム系)MOS(Excel・Wordの操作スキルを証明)などが、代表的な資格として挙げられるでしょう。
2.昇進や昇給を目指して目標を立てる
同じ職場で年収を上げたいと考えるなら、昇進や昇給を見据えた行動計画を立てることが重要です。役職が上がることで基本給だけでなく、賞与や各種手当の増加も見込めるため、年収アップに直結しやすくなります。
そのためにまずは、自社の評価制度や昇進基準を正確に把握することから始めましょう。「どのような実績が求められるのか」「上司は何を評価しているのか」を知ることで、具体的な行動目標が立てやすくなります。例えばプロジェクトのリーダーを任される、チームの数値目標を達成する、若手の育成を担うといった成果は、評価につながりやすいアピールポイントです。
3.副業を探してみる
収入を増やす手段として、副業は非常に有効です。働き方改革の浸透により、企業が副業を認めるケースも増えており、以前より始めやすい環境が整っています。すぐに収入を増やしたい場合は、アルバイトやフードデリバリー配達員といった労働型の副業がおすすめです。
一方で、Webライティングや広告運用、動画編集などのスキル型の副業は、将来的に単価を上げやすく、独立も視野に入れられます。自分のライフスタイルや目的に合わせて、副業の種類を選びましょう。
4.転職を考えてみる
現在の年収に不満がある場合、転職によって収入アップを目指すのが効果的です。まずは、転職サイトやエージェントを活用し、自分の市場価値を客観的に把握してみてください。
仮に期待より市場価値が低かった場合は、まず今の職場でスキルや実績を積み上げたり、興味のある業界や業種の資格を取得するなど、将来に向けて転職の可能性を広げることを考えてみましょう。一方で、現在の経験やスキルが高く評価されるのであれば、積極的に転職活動を進めて、より良い条件の企業を選ぶチャンスです。複数社から内定を得て比較検討することで、給与・働き方・成長環境など、希望に合った職場を見つけやすくなります。
今から将来に備えておくことが大事
年収600万円という水準は一見安定しているように見えますが、子どもの進学、住宅購入、老後の生活費など、将来的に必要な支出を賄うには十分とは言い切れません。特に家族を持つ場合、予測できない出費や長期的な負担が発生する可能性があるため、今のうちから将来に向けて備えておくことが大切です。ここでは、将来に備えるための方法を紹介します。
1.ライフプラン表を作成して目標を立てる
将来に向けて備え始める際に、まず取り組みたいのがライフプラン表の作成です。
ライフプランを立てることで、結婚・出産・住宅購入・教育資金・老後資金など、人生における大きな出費のタイミングが見えてきます。その結果、「いつ・どのくらいのお金が必要か」が明確になり、今なにを準備すべきかが具体的にイメージできるようになります。
しかし、初めての方にとっては「何から始めればいいかわからない」と感じるかもしれません。そんなときに便利なのが、フコク生命が提供しているライフプラン作成ツール「ライフコンパス」です。シミュレーションが完了すれば、将来の収支バランスや教育費・年金・公的保障などを踏まえたうえで、必要な資金と備えを可視化できます。将来のお金のイメージを明確にしたい場合は、ぜひライフコンパスを活用してみてください。
2.定期的に保険を見直しておく
ライフプランを立てたら、一緒に保険の見直しもおこないましょう。なぜなら、結婚・出産・住宅購入・子どもの進学など、ライフイベントによって必要な保障が変わるためです。
例えば、独身時代には最低限の医療保険で足りていたとしても、家族が増えれば死亡保障や教育資金への備えが必要になるかもしれません。逆に、ライフステージに合わない保険を継続し、過剰な保険料を払い続けているケースもあります。だからこそ、保険は一度入って終わりではなく、ライフステージごとに定期的な見直しが欠かせません。
しかし、どこをどう見直せばいいかわからないという方も多いでしょう。そんなときは、フコク生命が提供する「保険の見直しページ」や「保険商品一覧」を活用してみてください。今の生活に合った保障内容を把握することで、無理や無駄なく将来に備えられます。
3.iDeCoや新NISAを検討してみる
将来に向けた資産形成を考えるうえで、iDeCo(個人型確定拠出年金)や新NISA(少額投資非課税制度)の活用は非常に効果的です。どちらも国が用意した税制優遇制度で、長期的に見れば大きな節税効果と資産増加のメリットがあります。
iDeCoは、自分で掛金を積み立てて老後資金を準備する制度で、掛金の全額が所得控除の対象となります。運用益も非課税で、将来の年金として受け取ることが可能です。会社員や公務員、自営業など、立場に応じて拠出限度額が異なるため、自分に合った活用方法を調べておくと良いでしょう。
また、新NISAは2024年から制度が刷新され、より多くの人が柔軟に利用できるようになりました。投資によって得られる利益(売却益・配当)が非課税となり、資産を効率よく増やす手段として注目されています。
iDeCoや新NISAについてより詳しく知りたい方は、「【iDeCo】47都道府県、iDeCoを活用しているのはどこ?月々の掛金は?」や「【新NISA】いよいよ新NISA開始!47都道府県、新NISAにいくら投資する?」もご覧ください。
まとめ
年収600万円の手取りは年間おおよそ420万〜480万円、毎月の可処分所得は35万円前後と推測されます。単身世帯であれば比較的余裕のある水準ですが、家族がいる場合は家賃や教育費、生活費などの負担が重なり、貯蓄や将来の備えが難しく感じる場面もあることでしょう。
このような状況でも、スキルアップや資格取得、副業、転職などで収入を増やしたり、資産運用や保険の見直しで準備をしたりことで、将来に備えることが可能です。まずは自分の年収や支出を把握し、将来に向けて「何にどれだけお金が必要なのか」を整理することから始めてみましょう。
※本記事の内容は公開日時点の情報となります。法令や情報などは更新されていることもありますので、最新情報を確かめていただくようお願いいたします。
宮崎 千聖(みやざき ちさと)
FPライター。神戸大学経済学部卒業後、銀行の融資課にてローンの相談・手続きを担当した。退職後はライターとして、メガバンクや司法書士法人のオウンドメディアなどで記事を執筆。カードローンやクレジットカード、資産運用、債務整理など幅広いジャンルで執筆している。2級FP技能士、証券外務員一種








