
期間限定キャンペーン中!
Contents
就職や結婚、子育て、住宅購入など、人生のさまざまな場面で気になるのが「世帯年収」です。どのくらいの年収が一般的なのか、自分たちは平均と比べてどうなのか、気になって調べたことがある方も多いのではないでしょうか。
この記事では、世帯年収の基本である平均値や中央値との違いから気になる世帯の年収を、さまざまな年齢別や世帯タイプ別から見て詳しく解説します。
※本記事の内容は公開日時点の情報となります。法令や情報などは更新されていることもありますので、最新情報を確かめていただくようお願いいたします。
世帯年収とは
世帯年収とは、同じ世帯に属するすべての人の年間収入を合計した金額です。例えば、夫婦共働きであれば、夫と妻それぞれの年収を合計した金額が世帯年収となります。また、親子や兄弟などが同居していてそれぞれに収入がある場合も、その合計が世帯年収に含まれます。
ここで注意したいのが、年収と手取りは異なるという点です。年収は税金や社会保険料を差し引く前の金額であるのに対し、手取りはそれらを差し引いた後に受け取れる金額です。例えば年収400万円でも、手取り額は300万円台前半となるケースが多くなっています。
世帯年収の平均値と中央値の違い
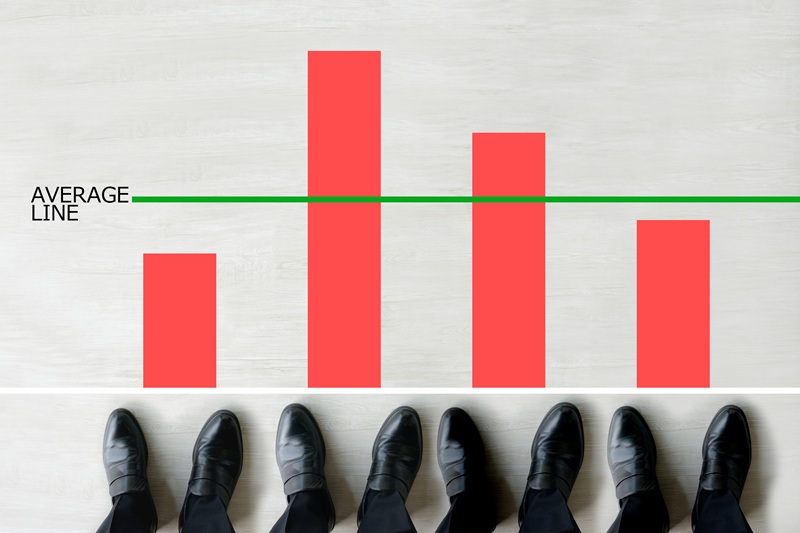
世帯年収の平均値は、すべての世帯年収を合計し、世帯数で割った数です。高収入の世帯が含まれていると、平均が大きく引き上げられるため、実態より高めに見える傾向があります。
一方で中央値は、世帯年収を低い順から並べたときに、真ん中に位置する世帯の年収です。極端に高い収入や低い収入に影響されないため、より一般的な世帯の実態に近い数値と言えます。
例えば年収が100万円、200万円、300万円、400万円、3,000万円の5世帯の平均値と中央値を求めてみましょう。平均値は(100+200+300+400+3,000)÷5=800万円となります。一方、中央値は真ん中の300万円です。
このように平均値と中央値には、大きな差が生まれるケースがあります。そのため、世帯年収を把握する際は、平均値だけでなく、中央値にも注目することで、現実に近い水準を理解しやすくなります。
全国の世帯年収の平均値・中央値
厚生労働省が公表している2023(令和5)年国民生活基礎調査によると、2022(令和4)年の1世帯当たり平均所得金額は524万2,000円、中央値は405万円です。2017年からの推移は以下の通りです。[参考1][参考2][参考3][参考4][参考5][参考6]
年次 世帯年収の平均値 世帯年収の中央値
| 年次 | 世帯年収の平均値 | 世帯年収の中央値 |
| 2017年 | 551.6万円 | 423万円 |
| 2018年 | 552.3万円 | 437万円 |
| 2020年 | 564.3万円 | 440万円 |
| 2021年 | 545.7万円 | 423万円 |
| 2022年 | 524.2万円 | 405万円 |
平均値と中央値では、100万円以上の差があります。ごく一部の高所得世帯が全体の平均を押し上げていることを示しており、平均より下の世帯が多数派の可能性があります。
また、2020年をピークに平均・中央値ともに緩やかに減少している背景には、コロナ禍における雇用環境の変化や、非正規雇用者の所得低下も影響しているでしょう。
今後、国としての賃上げ推進により、大企業を中心に中小企業まで賃上げが浸透すれば年収平均値や中央値の上昇の要因として考えられます。しかし、高齢化により、非労働の年金世帯が増加することで世帯年収を押し下げることも想定されるため、年収の平均値や中央値だけでは見えない世帯年収の多極化の可能性が見込まれます。
参考1:厚生労働省「2023(令和5)年国民生活基礎調査 各種世帯の所得等の状況」 1ページ
参考2:厚生労働省「2023(令和5)年国民生活基礎調査の概況」10ページ
参考3:厚生労働省「2018(平成30)年国民生活基礎調査の概況」10ページ
参考4:厚生労働省「2019(令和元)年国民生活基礎調査の概況」10ページ
参考5:厚生労働省「2021(令和3)年国民生活基礎調査の概況」10ページ
参考6:厚生労働省「2022(令和4)年国民生活基礎調査の概況」10ページ
年齢別の世帯年収の平均
世帯主の年齢によって、世帯年収の平均は異なります。厚生労働省の2023(令和5)年国民生活基礎調査によると、世帯主の年齢階級別にみた1世帯当たりの平均所得金額は以下の通りです。[参考7]
| 年齢階級 | 1世帯当たりの平均所得金額 |
| 29歳以下 | 339.5万円 |
| 30〜39歳 | 608.5万円 |
| 40〜49歳 | 696.0万円 |
| 50〜59歳 | 758.5万円 |
| 60〜69歳 | 536.6万円 |
| 70歳以上 | 381.0万円 |
この傾向は、ライフステージや働き方の変化が影響していると考えられます。例えば30〜50代は一般的にキャリアの伸び盛りであり、昇進や転職によって収入が増える時期です。加えて、配偶者も働く共働き世帯が増えることで、世帯全体の年収が高くなる傾向にあります。
一方、60代に入ると定年退職や再雇用といった働き方の変化により、現役時代と比べて収入が減少するケースが多くなります。70代では就労する人の割合がさらに下がり、年金などの公的給付を主な収入源とする世帯が増えるため、平均年収も大きく低下しているのでしょう。
参考7:厚生労働省「2023(令和5)年国民生活基礎調査 各種世帯の所得等の状況」 10ページ
共働き世帯や高齢者世帯の世帯年収を紹介
世帯年収は、働き方や家族構成によって大きく異なります。ここでは、夫婦共働き世帯・夫のみ有業の世帯・母子世帯や父子世帯・高齢者世帯の年収データを見ていきましょう。[参考8]
1.夫婦共働き世帯
総務省統計局の2024年家計調査(家計収支編)によると、夫婦共働き世帯の1ヵ月あたりの実収入は71万3,540円となっています。これを12ヵ月分に換算すると、年間の実収入は約856万円です。
共働き世帯は、夫婦それぞれが安定した収入を得ているため、全体として世帯年収が高くなりやすい傾向にあります。ここからは、子どもの有無に応じて世帯年収に違いがあるのかどうかも見ていきましょう。
1.1.夫婦のみの場合
総務省統計局の2024年家計調査(家計収支編)によると、夫婦共働きで子どものいない世帯の1ヵ月あたりの実収入は64万5,461円となっています。12ヵ月分に換算すると、年間の実収入は約775万円です。
夫婦のみの世帯は世帯主の平均年齢が54歳と中高年層が中心であり、子育て終了後の生活スタイルの変化や、健康・介護などの理由による就労調整が、世帯としての年収の低下に影響している可能性があります。
1.2.子ども1人がいる場合
総務省統計局の2024年家計調査(家計収支編)によると、夫婦共働きで子どもが1人いる世帯の1ヵ月あたりの実収入は71万1,377円です。12ヵ月分に換算すると、年間の実収入は約854万円になります。
子育て終了や役職定年、就労調整などを迎えた50代が中心となる子どもがいない夫婦共働き世帯と比べると高い傾向です。これは、子どもが1人いる世帯の平均世帯主年齢が46.3歳であることから、夫婦ともに40代の現役世代が多く、子どもの成長に向けて夫婦ともに就労重視の生活を送っていることが想定されます。また世代としても年収が伸びやすい時期にあることが考えられます。
1.3.子ども2人がいる場合
総務省統計局の2024年家計調査(家計収支編)によると、夫婦共働きで子どもが2人いる世帯の1ヵ月あたりの実収入は76万3,210円となっています。12ヵ月分に換算すると、年間の実収入は約916万円です。
子ども1人の世帯より高い水準となっており、共働きでもフルタイム勤務を維持している世帯が多い可能性がうかがえます。世帯年収が高くなることで、教育費や生活費の負担にも柔軟に対応できる状況といえるでしょう。
2.夫のみ有業の世帯
夫のみが働いている場合の世帯年収は、共働き世帯と比べて収入水準が下がる傾向にあります。総務省統計局の2024年家計調査(家計収支編)によると、夫のみ有業の世帯の1ヵ月あたりの実収入は57万3,405円です。12ヵ月分に換算すると、年間の実収入は約688万円となります。
ここからは、家族構成ごとに収入の違いを見ていきましょう。
2.1.夫婦のみの場合
総務省統計局の2024年家計調査(家計収支編)によると、夫のみが働いている夫婦のみの世帯における1ヵ月あたりの実収入は51万4,520円です。12ヵ月分に換算すると、年間の実収入は約617万円となります。
支出をコントロールしやすく、家計にゆとりが生まれやすい世帯が多い一方で、子育て世帯と比べると年収はやや低めです。これは、夫のみが働いていて夫婦のみの世帯は、世帯主の平均年齢が61.7歳であることから、定年前後の世帯が多いことが想定され、役職定年や早期退職後の再雇用などによって年収が減少しているケースが考えられます。
2.2.子どもが1人いる場合
総務省統計局の2024年家計調査(家計収支編)によると、夫のみが働いていて、子どもが1人いる世帯の1ヵ月あたりの実収入は58万9,389円です。12ヵ月分に換算すると、年間の実収入は約707万円になります。
保育園に預けることが難しく、妻が育児に専念している家庭もあるでしょう。夫のみが働いていて夫婦のみの世帯(世帯主平均年齢 61.7歳)と比べて年収が高いのは、世帯主が若いため(平均年齢 46.5歳)年収が伸びやすい時期であることや企業の福利厚生である家族手当などの加算が影響していると考えられます。
2.3.子どもが2人いる場合
総務省統計局の2024年家計調査(家計収支編)によると、夫のみが働いていて、子どもが2人いる世帯の1ヵ月あたりの実収入は64万8,379円です。12ヵ月分に換算すると、年間の実収入は約778万円です。
夫のみが働いていて子どもが2人いる家庭では、育児や家事の負担が大きく、妻が家庭に専念しているケースが多いとみられます。子ども1人の世帯より年収が大きく上がっているのは、扶養家族がさらに増えることによる家族手当の加算があるでしょう。また、世帯主が働き盛りのため(平均年齢 42.4歳)昇給や出世による年収アップも要因として考えられます。
3.母子世帯・父子世帯
厚生労働省の「令和3年度 全国ひとり親世帯等調査結果の概要」によると、ひとり親世帯では、母子世帯と父子世帯で平均年収に大きな差があります。[参考9]
| 母子世帯 | 父子世帯 | |
| 平均年間収入 [同居親族を含む世帯全員の収入] | 373万円 | 606万円 |
パートやアルバイトなど非正規雇用で働いている割合が高い母子世帯は、会社からの家族手当も受けにくい場合が多く、収入が安定しにくい傾向があります。一方で正規雇用の割合が高い父子世帯の平均年間収入は、母子世帯と比較すると高い水準です。また、会社から家族手当が支給されることにより、子どもがいない独身男性の世帯よりも、父子世帯の方が高年収のケースもあるでしょう。
4.高齢者世帯

高齢者世帯とは、65歳以上の方のみで構成される、または高齢者と18歳未満の未婚の方が同居した世帯を指します。厚生労働省の2023(令和5)年 国民生活基礎調査の概況によると、高齢者世帯の所得の平均値は304万9,000円です。[参考10]
高齢者世帯の主な収入源は公的年金であり、現役時代と比べると収入が減少します。また医療費や介護費などの支出が増える傾向にあるため、生活費などを抑えつつ貯蓄や年金の範囲内で堅実な暮らしをしている世帯が多いと考えられます。
参考8:総務省統計局「2024年 家計調査(家計収支編)家計収支編 二人以上の世帯」
参考9:厚生労働省「令和3年度 全国ひとり親世帯等調査結果の概要」1ページ
参考10:厚生労働省「2023(令和5)年 国民生活基礎調査の概況」11ページ
世帯年収によって生活スタイルは変わってくる?
自由に使えるお金に差があるため、世帯年収によって生活スタイルは変わります。同じ共働き世帯でも、子どもの有無や年収によって毎月の支出額や家計の余裕は異なります。総務省統計局の2024年家計調査をもとに、世帯年収500万円のケースと世帯年収800万円のケースでシミュレーションをしてみましょう。[参考11]
| 費目 | 年収450~500万円の月平均支出 | 年収750〜800万円の月平均支出 |
| 消費支出 | 276,773円 | 334,231円 |
| 食料 | 80,919円 | 91,696円 |
| 住居 | 17,810円 | 19,329円 |
| 光熱・水道 | 22,982円 | 24,325円 |
| 家具・家事用品 | 13,015円 | 14,543円 |
| 被服及び履物 | 7,386円 | 11,562円 |
| 保健医療 | 14,282円 | 14,683円 |
| 交通・通信 | 41,126円 | 45,852円 |
| 教育 | 3,104円 | 14,806円 |
| 教養娯楽 | 25,237円 | 34,351円 |
| その他の消費支出 | 50,911円 | 63,083円 |
まず注目したいのは食費の差です。世帯年収800万円の層では月あたり91,696円と、500万円層の80,919円よりも約1万円多くなっています。これは外食の頻度が増えたり、健康志向や品質重視の傾向が強まったりすることで、食材やサービスに対して積極的にお金をかける家庭が増えるためと考えられます。
最も差が大きいのは教育費で、500万円層では3,104円なのに対し、800万円層では14,806円と、実に5倍近い開きがあります。これは単に子どもの有無ではなく、高年収層ほど幼少期から教育にお金をかける文化や習慣が根づいていることが影響している可能性があります。年収が高くなるほど、学習塾や英会話など、早期教育への投資が日常化している世帯が多いと考えられるでしょう。
また、教育を重視する人々は、教養娯楽にも積極的に投資する傾向があります。年収500万円層が月25,237円の支出であるのに対し、800万円層では34,351円と、約9,000円の差があります。教育費が高い家庭ほど、教養娯楽にお金をかけることにより、家族全体の文化的教養や見識を広げることを重視していると考えられます。
例えば、美術館や博物館の訪問、音楽・演劇の鑑賞、さらには旅行を通じた異文化理解など、教育的価値を含む娯楽を選ぶことで、家庭の教育方針に合致した豊かな生活が育まれているのです。
このように教育と教養娯楽は、互いに補完し合う要素として、高年収層の生活スタイルに重要な位置を占めています。
参考11:総務省統計局「2024年 家計調査(家計収支編)家計収支編 二人以上の世帯 詳細結果表」
将来のために今から備えておくことが大事
世帯年収は現在の生活を支えるだけでなく、将来に向けた備えにも直結します。子どもの進学費用や住宅ローン、さらには老後の生活資金まで、人生の各ステージにはまとまった出費が発生します。特に老後は思うように働くことが難しくなるため、現役世代のうちから準備をしておくことが大切です。
収入が限られているなかでも、少しずつでも貯蓄や資産形成をおこない、ライフプランを立てることが、将来の安心につながります。そのためには、日々の家計を見直し、保険や投資などの制度も活用しながら、計画的に準備を進めていく必要があるでしょう。
また将来の不安に備えたい方には、「フコク生命 みらいプラス」の活用もおすすめです。月々5,000円から始められる個人年金保険で、加入から年金開始までの期間が長いほど返戻率(年金総額÷保険料累計)も高くなります。
さらに、生命保険料控除の対象となるため、節税と老後資金の準備を同時に実現できる商品です。早めに準備を始めることで、将来の選択肢が広がります。将来に向けた備えとして、「フコク生命 みらいプラス」での資産形成を検討してみてはいかがでしょうか。
まとめ
世帯年収は、家庭全体の収入を合算した金額です。生活レベルの目安になるだけでなく、将来のライフプランを考える際の基準になります。
全国の世帯年収の平均値は約524万円、中央値は約405万円とされており、自分たちの年収がどの位置にあるかを知ることで、今後の暮らし方や資金計画を見直すきっかけになるでしょう。また年齢や家族構成によっても世帯年収は大きく異なりますが、同じ年収でも支出のバランスや備え方次第で、将来の安定度は変わってきます。
家計の見直しや節税制度の活用、保険や投資による資産形成など、世帯年収を効果的に活かす工夫が将来の安心につながります。まずは自分たちの世帯年収を正確に把握し、将来に向けてできることから始めてみましょう。
※本記事の内容は公開日時点の情報となります。法令や情報などは更新されていることもありますので、最新情報を確かめていただくようお願いいたします。
宮崎 千聖(みやざき ちさと)
FPライター。神戸大学経済学部卒業後、銀行の融資課にてローンの相談・手続きを担当した。退職後はライターとして、メガバンクや司法書士法人のオウンドメディアなどで記事を執筆。カードローンやクレジットカード、資産運用、債務整理など幅広いジャンルで執筆している。2級FP技能士、証券外務員一種
記事提供元:株式会社デジタルアイデンティティ








