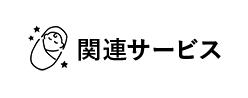期間限定キャンペーン中!
Contents
「子どもの反抗期はいつからいつまで続くのか心配」「子どもが突然反抗的になり、どう対応すべきかわからない」とお悩みのママパパはいませんか?
今回は、反抗期の時期の目安から原因、そして年齢別の反抗期の特徴まで詳しく解説。さらに日々の暮らしに役立つ、反抗期の子どもへの接し方や声かけのコツ、知っておきたい親の心構えまで紹介しています。
※本記事の内容は公開日時点の情報となります。法令や情報などは更新されていることもありますので、最新情報を確かめていただくようお願いいたします。
そもそも反抗期とは?
反抗期とは、子どもが自立への道を歩み始める過程で、親への反発や自分の意見を主張するようになる時期のことを指します。親としては、今まで素直だった子が急に口答えしてくるなど、態度が一変するため、戸惑ってしまうものです。しかし反抗期は、子どもが精神的に自立しようとする成長過程のひとつ。親から離れ、自分の考えで行動できるようになっていくための準備期間なのです。
1. 反抗期の原因
反抗期は、子どもが急激な体の変化や環境の変化に、戸惑いやストレスを感じることが原因でおこりやすいといわれています。年齢によって異なりますが、例えば、自我が芽生える、ホルモンバランスが変化するなど、さまざまな要因が重なり、自分自身を理解できなかったり、イライラを感じたりします。
例えば、親の指示が「うるさい」と感じ、反抗的な態度を取ることもありますが、親からすれば、心配ゆえのこと。このように、親の言動がきっかけになることもありますが、親の育て方が悪いというわけではありません。反抗期は「子ども自身が自分と親との適切な距離感を探っている時期」であると捉えましょう。
2. 反抗期がこない子どももいる
なかには「よその子は反抗期で大変そうなのに、うちの子は全然…」と感じている親御さんもいるかもしれません。子どもの成長や発達のスピードには個人差があります。反抗期も子どもによって異なり、長引く子もいれば反抗期がこない子どももいます。実は、これはとくに珍しいことではありません。
反抗期がわかりにくい、あるいはこない理由としては、以下のようなものが考えられます。
【反抗期がわかりにくい、こない理由】
- 親側が反抗と認識していない
- 子どもの気質が内向的・穏やかである
- 親子関係が良好である
- 親による強い支配や抑圧がある
- 甘やかされすぎている
- 精神的な不調がある
親が反抗を見逃したり、子ども自身が穏やかで反抗心を内に秘めたり、信頼に基づいた良好な親子関係も反抗を目立たなくさせます。これらは自己主張が別の形で健全に表現されている場合もあります。
逆に、過度な支配下で反抗する気力を失っていたり、甘やかしていたりすることによって自立心が育ちにくい状況では、反抗期が健全に訪れないことがあります。さらに、そうした環境が引き金となり精神的な不調を引き起こし、反抗するエネルギー自体を奪っているケースも考えられます。
いずれの場合も、言葉にならないサインを見逃さず、子どもの内面の変化に注意深く気を配り、対話を続ける姿勢が大切です。
反抗期はいつからいつまで?特徴は?
「子どもの反抗期はいつから始まるの?」と気になっているママパパも多いかもしれません。実際には子どもに反抗期が訪れるのは個人差があるため、その時期には統一された基準はありませんが、大きくわけておおよそ次の3つの時期とされています。
【反抗期の主な時期は3つ】
- 第一次反抗期(1歳半頃~3歳頃)
- 中間反抗期(5歳頃~10歳頃)
- 第二次反抗期(男の子は10歳頃~、女の子は11歳頃~高校生頃)
では、それぞれの反抗期の特徴を詳しく見ていきましょう。
1. 第一次反抗期
通称「イヤイヤ期」として知られ、「魔の2歳児」と呼ばれることもある第一次反抗期。期間は、1歳半から3歳頃までが目安です。
この時期の子どもは、さまざまなことに対して「自分でやる!」など自己主張するようになることが多いです。自我の芽生えと「できた」という自信が増える一方で、自分ではこなせないことに対する葛藤が、子どもの癇癪につながります。
例えば「靴下は履きたくない!」「自分でお着替えする!」など親が手を貸すのを拒否することが増え、うまく伝えられず「イヤ!」というひと言で主張することがよくあります。これは、自己主張できるほど成長してきているという証拠だといえるでしょう。
2. 中間反抗期
第一次反抗期ほど激しくはないものの、反抗的な態度が見られる中間反抗期。期間は、主に小学校に入学する5歳頃から10歳頃までが目安です。
この時期の子どもは、交友関係の広がりや入学・進級など環境の変化によるストレスが溜まることにより、親のいうことを聞かなくなったり、言葉遣いが悪くなったりすることが増えてきます。また、友達からの影響力が強くなってくる傾向もあります。
例えば「宿題なんてやりたくない!」とダラダラする、友達の真似をして新しい言葉を使い始める、物にあたるといった反抗的な態度が挙げられます。これは自我がさらに成長している証だといえるでしょう。
小学生時代における中間反抗期について詳しく知りたい方は、「「4歳の壁」とは?小1・小4の壁との違いや乗り切る方法、注意点について」や「「小4の壁」とは?小1の壁との違いや起こる原因・対策方法について詳しく解説」もぜひ参考にしてください。
3. 第二次反抗期

本格的な反抗期といわれ、一般的に一番長く続くことが多いとされる第二次反抗期。期間は10歳頃から始まり12歳頃まで、長ければ高校生まで続くこともあります。
この時期の反抗期は思春期とも重なるため、ホルモンの急速な変化によって心身が不安定になりがちです。また、さらに友達との集団行動を重視するようになっていきます。客観視できるようになったことから抱く劣等感など、人間関係でのストレスも抱えることが多くなるのです。これが親にあたる態度につながります。
例えば「友達と遊びに行きたい」など家族との時間よりも自分の時間を優先するようになったり、親のルールに反発したりするようになることも増えます。これは、社会生活で必要な自立心や仲間意識を鍛える訓練過程のひとつだといえるでしょう。
どの時期も、お子さんの成長過程で大切な時期です。時期や長さ、特徴は目安ですので、お子さんの様子をよく観察して、個々に合った対応をすることが重要だといえます。
反抗期の接し方と声かけのコツ
反抗期の子どもは、態度や行動でとにかく反抗してくるため、親としては接し方に悩むものです。こちらでは、子どもの反抗期で悩んでいる方へ向けて、ぜひ押さえておきたい接し方と声かけのコツを8つご紹介します。
反抗期の接し方、声かけのポイント8つ
- 頭ごなしの否定はしない
- 最後まで話を聞く
- 子どもの気持ちを代弁する
- 子どもの自主性を尊重する
- 子どもがひとりで過ごす時間をつくる
- 子どものストレスを上手に逃がしてあげる
- 小さな成長も見逃さずに認める
- 感情的にならない
では、それぞれ詳しく説明していきましょう。
1. 頭ごなしの否定はしない
対象年齢:反抗期全般、とくに第一次反抗期(1歳半頃~3歳頃)
子どもは親に頭ごなしに否定されると、自分自身を全否定されたような気持ちになり、傷つくことがあります。とくに幼児時代の第一次反抗期は、子どもが自分の意見を持ち始める重要な時期です。そのため、否定されると自己肯定感が下がる原因にもなります。最初から「ダメ!」というのではなく、まずは子どもの気持ちを理解しようと努めることが大切です。
例えば、おもちゃの取り合いで「ダメ!」ではなく、「貸して欲しかったんだね。でも、順番に遊ぼうね」とやさしく声かけしましょう。宿題をせずにゲームばかりしている子どもに対しては「ゲーム、楽しいんだね。でも、宿題を終わらせないと困るよね。どうすればできるかな?」と共感から始め、解決策を一緒に探る手助けをしましょう。
2. 最後まで話を聞く
対象年齢:反抗期全般、とくに中間反抗期(5歳頃~10歳頃)
とくに小学生時代の中間反抗期は、子どもが感情を言葉にする練習期間であり、子どもが自立するためには、自分の意見を相手に伝える力が必要になります。しかし、せっかく話していても親に話を遮られてしまうと、子どもは「どうせ聞いてもらえない」と自分の気持ちを表に出すのを諦めてしまうようになります。親の意見を押し付けず、最後まで子どもが自分のペースで話せるように促すことが大切です。
例えば、子どもが学校で友達とケンカした出来事を、愚痴として親に話してくることもあるでしょう。そんなときは、途中で「それは違うよ」など反論せず、最後までじっくり耳を傾けましょう。中高生になり、子どもが学校であったことを話したがらないときでも「話したくなったらなんでも聞くよ」と伝え、待つ姿勢を見せることも大切です。「親はいつでも味方でいてくれる」と感じることが、精神的な自立につながります。
3. 子どもの気持ちを代弁する
対象年齢:反抗期全般
反抗期にいる子どもは、心身や環境の変化に対応できず、複雑な感情を抱えがちです。そんなときは「こう感じているんじゃないかな?」と子どもの気持ちを代弁してあげることで、子どもは自分の感情を整理・理解しやすくなります。また「自分の気持ちを理解してもらえた」という安心感を子どもに与えます。
例えば、子どもがイライラしている様子を感じたら「なにか嫌なことがあったのかな?」、子どもがスポーツのチームでレギュラーが取れずに落ち込んでいたら「悔しかったね」などと声をかけてあげましょう。そのときの子どもの気持ちを優しく推測するような言葉が効果的です。
4. 子どもの自主性を尊重する
対象年齢:反抗期全般、とくに第二次反抗期(10歳頃~高校生頃)
子どもの自主性を尊重することは、自立心や自己主張の力を育てるために重要な項目です。子どもが自分で考え、決める機会を積極的に与えるようにしましょう。とくに思春期と重なる第二次反抗期では、親が過剰に介入しようとすると、反発心を強める可能性がありますので注意が必要です。
例えば「早く宿題をやりなさい」と一方的に指示するのではなく「宿題は何時からやる予定なのかな?」など、子どもに自分で決める経験をさせていきましょう。その選択を尊重することで、子ども自身も自分の選択に責任を持つようになります。例え失敗したとしても「次はどうすれば良いと思う?」と振り返りのチャンスを与えることで、子どもはさらに成長する機会に恵まれます。
5. 子どもがひとりで過ごす時間をつくる
対象年齢:第二次反抗期(10歳頃~高校生頃)
主に中学生から高校生頃の第二次反抗期の子どもにとって、ひとりで過ごす時間や部屋にこもるという行動は、成長過程において自然であり、必要なことでもあります。そこで親ができるのは、子どもがひとりでリラックスできる居場所を提供すること。親は過剰に干渉せず、子どものプライバシーを尊重しつつ見守る姿勢が大切です。
子どもが自分の部屋にこもりそうな気配がしたら「今日はゆっくり休んでね」「なにか相談ごとがあったら声をかけてね」と安心感を与えつつ、距離感を保つようにしましょう。こうした姿勢が信頼関係を深め、子どものストレス軽減にもつながります。
6. 子どものストレスを上手に逃がしてあげる
対象年齢:反抗期全般、とくに中間反抗期(5歳頃~10歳頃)・第二次反抗期(10歳頃~高校生)
子どもの反抗的な態度や行動の裏には、友人関係や学校でのストレスが隠れていることがあります。しかし、子どもはストレスが溜まっても、どう扱えば良いのかわからず感情が爆発してしまうことも。子どものストレスに気づけるよう注意を払いつつ、子どもの好きな遊びや趣味、運動などを利用して、ストレス発散の機会を作ってあげることも大切です。
例えば、子どもがイライラしていることに気づいたら、まずは「最近がんばっているね。でも疲れてないかな?」などまずはさりげなく声をかけ、子どもの様子を伺います。そして「今日は一緒にショッピングに行って気分転換しようか?」など、寄り添う言葉をかけてみましょう。無理なく意識的にストレスを減らす活動を取り入れ、子どもの心の健康をサポートしていくのがポイントです。
7. 小さな成長も見逃さずに認める
対象年齢:反抗期全般
反抗期の子どもと毎日顔を合わせていると、反抗的な態度にばかりつい目が行きがちです。しかし子どもとしては、反抗した後に怒られた記憶ばかりが残ってしまい、自己肯定感の低下につながります。そのため反抗期であっても、子どもの小さな成長や努力を見逃さず、積極的に褒めることも大切です。ちょっとしたことでも努力や成果を褒める習慣を続けることで、子どもは自信を持つようになっていくものです。
例えば、自分の部屋を片付けたら「きれいになったね、よくがんばったね」、お手伝いをしてくれたら「〇〇してもらえて助かったよ、ありがとう!」など、行動を具体的に褒めましょう。子どもは大好きな親に褒められることで、自分の存在価値を認められるようになっていきます。
8. 感情的にならない
対象年齢:反抗期全般
反抗期には子どもだけでなく、親もつい感情的になりがちです。しかし、反抗期における親子関係の安定にもっとも必要なのは「親自身の冷静さ」です。親が冷静さを保つことで、子どもも落ち着きやすくなります。
例えば、子どもが感情的に怒鳴ってきたときでも、深呼吸をする、数秒間待つなどしてから「落ち着いて話せる?」と穏やかに対応しましょう。それでも子どもがなかなか落ち着かない場合は「少し休憩してから話そうか」と声をかけ、子どもに安心感を与えましょう。間を空けることで、子どもも冷静さを取り戻しやすくなるものです。
反抗期に振り回されないための親の心構え

反抗期は、子どもだけでなく親にとっても大きなストレスとなる時期です。こちらでは、つらいこの時期を少しでも楽に乗り越えるために、気持ちの持ち方やストレスとの向き合い方を4つご紹介します。
反抗期に振り回されないための親の心構え
- 完璧を目指さない
- ひとりで抱え込まない
- 自分の時間をつくる
- 反抗期には終わりがあることを忘れない
1. 完璧を目指さない
「良き母」「良き父」であろうと頑張りすぎていませんか?子育てに100点満点はありません。反抗期の子どもへの対応は毎日が試行錯誤ですので、うまくいかない日があっても当たり前です。
大切なのは「子どもと向き合おうとする気持ち」と、失敗を振り返りつつも自分を責めずに受け入れることです。子育ての完璧を目指して自分を追い込むのではなく、親として少しずつ成長している自分のことも大切に。「今日はうまくいかなかったけど、明日がある!」と少しでも前向きに捉え、心の負担を軽くしましょう。
2. ひとりで抱え込まない
「うちの子だけ…」「私だけこんなに大変…」なんて思っていませんか?反抗期の子育ては孤独感をともなうことが多いですが、ひとりですべてを抱え込むのではなく、誰かに話してみることをおすすめします。パートナーや友人、学校の先生など、身近な人に気持ちを聞いてもらうだけでも気持ちが楽になりますし、思わぬヒントが得られることもあります。
また、子育ての専門家である公的な相談窓口や、子育て支援センター、スクールカウンセラーなど、相談できる場所は多数あります。ひとりきりで悩まず、周りの力を借りて乗り越えましょう。
3. 自分の時間をつくる
反抗期の子どもと過ごす毎日は、つい子どものことばかり考えてしまいがち。自分のことは後回しにしてしまう親御さんも多いのではないでしょうか。しかし、それでは心も体も疲れてしまいますので、親自身の時間を持つことも大切です。
例えば、家族や支援施設に子どもを預けて、映画を観たりランチを楽しんだりなど、好きなことをして過ごすのも良いでしょう。自分自身をいたわり満たすことで、心にもゆとりが生まれ、子どもとの関係もより良いものになっていくはずです。
4. 反抗期には終わりがあることを忘れない
今まさに反抗期の真っ只中で、毎日が嵐のように感じている親御さんもいるでしょう。子どもの言動に傷ついたり、「もう限界!」と思ったりする日もあるかもしれませんが、反抗期には終わりがあります。
子どもは親の想像以上に成長しています。今は反抗しているように見えても、実はちゃんと親のことを見て、考え学んでいるのです。「子どもはちゃんと成長している」と信じる心が、子どもとの関係をより深いものにしてくれます。そして、いつか振り返ったときに「あの頃はよくがんばった!」と自分自身を褒めてあげられるはずです。
子どもの反抗期とうまく付き合うためには、親のストレス発散も大切です。「育児ストレスを感じる原因は?ストレスへの対処法や改善方法についても紹介」もぜひ参考にしてください。自分に合った方法を見つけて、反抗期を乗り越えましょう。
まとめ
反抗期とは、子どもが自立へ向かう成長過程で親への反発や自己主張が見られる時期のことであり、主に1歳半頃から高校生の間に現れるといわれています。しかし、なかには反抗期がやってこない子どももいます。反抗期には、個人差があるため、子どもの様子をよく見ながら、個々に合わせて対応していくことになります。
この時期を乗り越えるためには、親は子どもの気持ちを理解し、適切な接し方をすることが大切です。感情的にならず、ひとりで抱え込まず、信頼を持って子どもを見守る姿勢が、より良い親子関係を築く手助けになります。反抗期は一時的なものですので、親も自分の時間を大切にしながらストレスを軽減するとともに、その成長を見守りましょう。
※本記事の内容は公開日時点の情報となります。
法令や情報などは更新されていることもありますので、最新情報を確かめていただくようお願いいたします。
是枝花名子(これえだ かなこ)
FPライター。大学卒業後、大手生命保険会社にて法人営業を担当。住宅ローンの繰り上げ返済、子どもの教育資金や老後資金作りを極めるため、改めてFP技能士を取得。専門知識と主婦目線を活かした記事執筆が好評を呼び、現在は主にメガバンク、大手不動産サイト等にて保険・不動産・翻訳ライターとして活動中。2級FP技能士
記事提供元:株式会社デジタルアイデンティティ