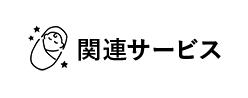期間限定キャンペーン中!
Contents
この記事を読んでいる人におすすめ!

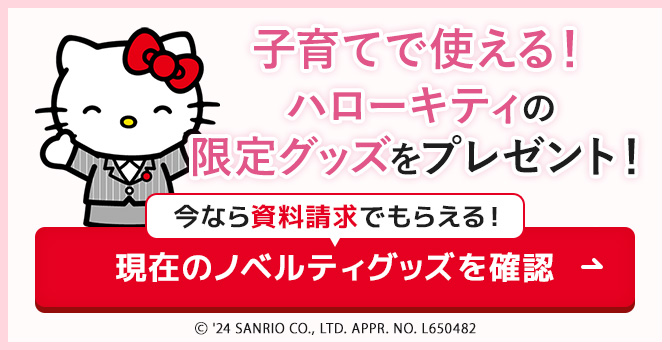
保育園へ入園を検討するにあたって、「何歳から入園できるのか」あるいは「何歳で入園するのがいいのか」といった疑問を抱く方は少なくありません。
この記事では、入園する年齢ごとのメリット・デメリットと、入園までの流れや注意点について解説します。
※本記事の内容は公開日時点の情報となります。法令や情報などは更新されていることもありますので、最新情報を確かめていただくようお願いいたします。
保育園は何歳から入園できるの?
保育園には、0歳(生後57日以降)から入園可能です。ただし、誰でも入園できるわけではありません。保護者に保育を必要とする事由があり、家庭での保育が難しいことが条件になっています。保育を必要とする事由とは、次のようなものです。[参考1]
【保育を必要とする事由】
- 就労
- 妊娠、出産
- 保護者の疾病、障害
- 同居または長期入院などをしている親族の介護、看護
- 災害復旧
- 求職活動(起業準備を含む)
- 就学(職業訓練校などにおける職業訓練を含む)
- 虐待やDVのおそれがあること
- 育児休業取得中に、すでに保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
- その他、上記に類する状態として市町村が認める場合
参考1:内閣府「よくわかる「子ども・子育て支援新制度」」保育認定(2号・3号)について
幼稚園・認定こども園との違い
子どもを預けられる施設には保育園のほか、幼稚園と認定こども園があります。それぞれの特徴と違いは次のとおりです。[参考2]
- 幼稚園:小学校以降の教育の基礎をつくるための幼児期の教育をおこなう学校
- 保育園(保育所):就労などのため家庭で保育のできない保護者に代わって保育する施設
- 認定子ども園:幼稚園と保育園の機能や特長をあわせ持ち、地域の子育て支援もおこなう施設
各施設の対象年齢・認定区分・利用時間・利用できる保護者
| 施設 | 年齢 | 認定区分 | 利用時間 | 利用できる保護者 |
| 幼稚園 | 3歳〜5歳 | 1号認定 (教育標準時間認定) | 昼過ぎごろまでの教育時間に加え、園により午後や土曜日、夏休みなどの長期休業中の預かり保育などを実施 | 制限なし |
| 保育園 (保育所) | 0歳〜2歳 | 3号認定 (保育認定) | 夕方までの保育のほか、園により延長保育を実施 | 共働き世帯、親族の介護などの事情で家庭保育ができない保護者 |
| 3歳〜5歳 | 2号認定 (保育認定) | |||
| 認定こども園 | 0歳〜2歳 | 3号認定 | 夕方までの保育のほか、園により延長保育を実施 | 共働き世帯、親族の介護などの事情で家庭保育ができない保護者 |
| 3歳〜5歳 | 1号認定 (短時間利用) 2号認定 (長時間利用) | 昼過ぎごろまでの教育時間に加え、保育を必要とする場合は夕方までの保育を実施 園により延長保育も実施 | 制限なし |
参考2:内閣府「よくわかる「子ども・子育て支援新制度」」新制度で増える教育・保育の場/認定について
保育園の入園がベストな時期はいつ?

入園のしやすさでは、競争率が低い傾向のある0歳または3歳がよいといえます。
こども家庭庁の2024年度調査によると、保育園の待機児童数は1歳児と2歳児が8割強を占めています。[参考3]
年齢区分別の利用児童数・待機児童数
| 利用児童数(割合) | 待機児童数(割合) | |
| 0歳児 | 131,247人(4.9%) | 161人(6.3%) |
| 1歳児・2歳児 | 964,302人(35.6%) | 2,178人(84.8%) |
| 3歳児以上 | 1,609,509人(59.5%) | 228人(8.9%) |
| 全年齢計 | 2,705,058人(100.0%) | 2,567人(100.0%) |
ただし、入園する年齢ごとにメリット・デメリットはあるため、家庭の事情や子どもの成長に合わせて考えることが大切です。
参考3:こども家庭庁「保育所等関連状況取りまとめ(令和6年4月1日)」2.保育所等待機児童数の状況
1.0歳 で入園
0歳で保育園に入園するメリットには、次のようなものがあります。
【0歳で入園するメリット】
- 競争率が低く入園しやすい
- 早い時期から集団生活を送ることで、基本的な生活習慣や社会性が身に付きやすくなる
- 子どもの発達・成長段階に応じた保育を受けられる
- 保護者が早期に復職できる
- 育児の負担やストレスが軽減される
原則として子どもが1歳(※)になるまでは育休を取得できることから、1歳で入園を希望する方が多く、競争率は0歳児クラスのほうが低い傾向があります(※保育園などに預けられないなどの事情がある場合は、最長2歳まで延長可能) 。[参考4]
また、早い時期から家族以外の人と関わり集団生活を送ることで、基本的な生活習慣や社会性が身に付きやすくなります。保育のプロである保育士に子どもの発達・成長段階に応じた保育を受けられる点もメリットといえるでしょう。
保護者にとっては早期の復職が可能になり、収入やキャリアへの影響を抑えられる点が大きなメリットです。かわいい子どもとはいえ、常に接しているとストレスを感じてしまう方も少なくありません。子どもを預けて仕事をすることで気分転換になり、育児の負担やストレスを軽減する効果も期待できます。
メリットの反面、次のようなデメリットもあります。
【0歳で入園するデメリット】
- 感染症などにかかるリスクが高くなる
- 親子で過ごす時間が少なくなる
生後半年から1歳半頃までは一生のうちで最も免疫力が低い時期であり、多くの子どもと集団生活を送ることで感染症などの病気にかかるリスクが高くなります。
また、早期に復職すれば親子で過ごせる時間が減ってしまいます。もっと子どもと一緒に過ごしたいと思う方もいるでしょう。
参考4:厚生労働省「育児休業期間の延長」
2.3歳 で入園
3歳で入園するメリットには、次のようなものがあります。
【3歳で入園するメリット】
- 競争率が低く入園しやすい
- 保育料が無料になる
- 親子で過ごす時間を長く確保できる
- コミュニケーションが取れる年齢であり、園に馴染みやすい
3歳児クラスは定員が増えたり幼稚園への転園により枠が空いたりすることで、1歳児クラスや2歳児クラスに比べて競争率が低く、希望する園に入園しやすい傾向があります。
また、3歳から5歳までの保育料は、幼児教育・保育の無償化ですべての子どもについて無料になっており、経済的な負担を抑えられます。
3歳まで家庭で保育するため親子で過ごせる時間を長く確保できる点、コミュニケーションが取れる年齢になり、園での生活や新しい環境に馴染みやすい点などもメリットといえるでしょう。
【3歳から入園するデメリット】
- 育休が最長でも2歳で終了するため、3歳までの間の保育をどうするか考える必要がある
- 持ち上がりのコミュニティができていると入っていきにくいことがある
育休は最長でも2歳までであり、入園までの間に復職する場合には仕事中の保育をどうするのか考えなければなりません。
また、3歳より前に入園した子どもや保護者でコミュニティができあがっていることもあり、途中からその中に入っていきにくいといった問題もあります。
3.その他の年齢で入園
その他の年齢での入園では、それぞれ次のようなメリット・デメリットがあります。
| メリット | デメリット | |
| 1歳 | ||
| 2歳 | ||
| 4歳・ 5歳 |
1歳、2歳での入園は、育休の終了にあわせて入園させられるといったメリットがあります。一方で競争率の高さがネックです。
4歳、5歳での入園は、競争率が比較的低いなどのメリットがありますが、入園までの保育をどうするのかを考えなければなりません。
保育園に入るまでの流れ・スケジュール

認可保育園へ4月に入園する場合、一般的に次のような流れで手続きを進めていきます。
●4~6月:情報収集や自治体に相談をして条件の合う保育園を絞り込みましょう
まずは周辺の保育園情報を収集しましょう。自治体の保育課などに相談すると保育園の案内資料をもらうことができます。集めた資料をもとに、まず条件に合う保育園を絞り込むことが大切です。
●7~9月:保育園の見学をおこない、希望園を決定しましょう
候補となる保育園が決まったら、見学の申し込みをおこないましょう。実際に園を訪れて、雰囲気や設備を確認し、入園後の生活を考慮して希望園を決定することが重要です。
●10~12月:入園申込の準備をし、必要書類を提出しましょう
この時期には、自治体から来年度の募集要項をもらいます。そのうえで、保育園の申込書類を記載し、勤務証明書など必要な書類を用意し、自治体の保育課など指定提出先に期日までに提出します。
●1~2月:入園内定を確認し、決まらない時は二次募集情報を収集しましょう
新年早々、内定通知が届きます。内定が決まったら入園説明会に参加し、準備を進めていきましょう。もし一次募集で不承諾の場合は、二次募集をおこなっている保育園を探し、すぐに応募することをおすすめします。
自治体によってスケジュールが異なるため、早めに情報を確認し、準備を整えておきましょう。
保育園入園を検討する際に気をつけるべきポイント
保育園入園を検討する際は、次のようなポイントに気を付けるとよいでしょう。
1.見学をしておく
入園後に希望と違ったということがないよう、申し込み前に気になる園は見学しておくのがおすすめです。見学では次のようなポイントを確認しましょう。
- 保育時間
- 延長保育の有無や時間・料金(私立保育園の場合)
- 保育指針や保育目標など園の特徴
- 保育内容や在園児の様子
- 屋内外の環境や設備
- 給食・おやつの内容やアレルギー対応
見学は予約制となっていることが多いため、あらかじめ園に確認し、予約してから見学に行きしましょう。
2.費用について把握しておく
保育園の費用についても把握しておきましょう。[参考5]
認可保育園の費用(保育料)は、国の基準をもとに市区町村ごとに定めることになっており、子どもの年齢や保育の必要量(保育時間)、世帯所得(市区町村民税の所得割額)によって決まります。公立・私立による違いはありません。
一方、認可外保育園の費用(保育料)は各施設が自由に設定できるため、施設ごとに差があります。
また保育料は「幼児教育・保育の無償化」により大きく変動するため、その内容も理解しておきましょう。
- 認可保育園
3〜5歳児の保育料と住民税非課税世帯の0〜2歳児の保育料は無料です。
上記のほか、子どもが2人以上いる世帯は、小学校就学前の最年長の子どもを第1子とカウントして、0〜2歳までの第2子は半額、第3子以降は無償になります。
- 認可外保育園
市区町村から「保育の必要性の認定」を受けて利用する場合に補助が受けられ、3〜5歳児は月額3.7万円まで、住民税非課税世帯の0〜2歳児は月額4.2万円までは利用料が無料になります。
さらに各自治体が独自の補助制度を実施している場合もあるため、お住まいの自治体に確認するようにしましょう。
実際の費用の目安など、保育園の費用について詳しく知りたい方は「保育園の費用はどれくらい?認可と認可外の違いや無償化についても詳しく解説」をご覧ください。
参考5:こども家庭庁「幼児教育・保育の無償化概要」
3.落ちてしまった場合の対策を考えておく
希望する園に入園できないことも想定して対策を考えておくことも大切です。
1次募集で内定が得られなくても、定員割れになった園の追加募集、入園辞退者が出たことによる再募集で内定が得られるケースもあります。入園保留になると、自動的に2次募集の選考に回される自治体もありますが、ご自身でも情報を集めてチャンスを逃さないようにしましょう。
認可保育園だけでなく、認可外保育園や地域型保育(※)、一時預かりサービスベビーシッターなどの活用も選択肢になります。
※保育園(原則20人以上)よりも少人数の単位で、0〜2歳の子どもを保育する事業のこと。家庭的保育(保育ママ)、小規模保育、事業所内保育、居宅訪問型保育の4つのタイプがある。
まとめ
保育園に入園しやすい時期は0歳や3歳とされていますが、最適なタイミングは家庭の事情や方針、子どもの成長度合いなどによっても異なります。早めに情報収集をおこない、スケジュールや費用を把握したうえで、計画的に準備しておくことが大切です。
※本記事の内容は公開日時点の情報となります。法令や情報などは更新されていることもありますので、最新情報を確かめていただくようお願いいたします。
竹国弘城(たけくに ひろき)
独立系FP、RAPPORT Consulting Office代表。証券会社、生損保代理店での勤務を経て独立。お金に関する相談や記事の執筆・監修を通じ、自分のお金の問題について自ら考え、行動できるようになってもらうためのサポートを行う。1級ファイナンシャルプランニング技能士、CFP®、証券外務員一種、宅地建物取引士
記事提供元:株式会社デジタルアイデンティティ