
期間限定キャンペーン中!
毎月の支出で大きな割合を占める食費の節約は、多くの人の関心事です。
この記事では、一人暮らしと二人暮らしの平均的な食費を示しながら、食費の効果的な節約方法と注意点を詳しく解説します。また、家計簿をつけたり、保険を見直したりといった食費以外の節約方法についても紹介します。食費を中心に生活全般の節約を実践することで、さらにゆとりのある生活を目指しましょう。
※本記事の内容は公開日時点の情報となります。法令や情報などは更新されていることもありますので、最新情報を確かめていただくようお願いいたします
1ヵ月の食費の平均
毎月の生活費の中でも大きな割合を占めるのが食費です。一人暮らしと二人暮らしでは、どのくらいの費用が一般的なのでしょうか。ここでは、一人暮らしと二人暮らしの平均的な食費の目安を比較します。
1.一人暮らしの食費
2023年の家計調査によると、一人暮らしの人は1ヵ月あたり平均42,049円を食費として使っていることがわかりました。[参考1]
食費の使い道を見てみると、最も大きな割合を占めているのは外食費で9,690円、続いて調理食品費が7,618円となっています。これらの外食費と調理食品費を合わせると17,308円となり、食費全体の約41.2%を占める結果となりました。[参考1]
一方、魚介類、肉類、乳卵類、野菜・海藻、果物といった生鮮食料品を合計すると11,900円で食費全体の約28.3%となっています。[参考1]
参考1:総務省統計局 e-Stat「家計調査 2023 1世帯当たり1か月間の収入と支出 世帯人員・世帯主の年齢階級別」
2.二人暮らしの食費
二人暮らしの家庭では、月の食費は72,399円で、一人当たり36,200円になります。これは一人暮らしの平均的な食費42,049円と比較すると低い金額です。[参考2]
食費の内訳を見ると、調理食品が11,056円と最も多く、次いで外食費が9,483円で、両者を合算すると食費全体の約28.4%となります。これは、一人暮らしの外食・調理食品費の41.2%よりもかなり低い割合です。[参考2]
一方で、生鮮食料品は合計28,592円で食費に占める割合は約39.5%となっており、一人暮らしの28.3%を上回っています。[参考2]また、一人当たりの金額を見ると一人暮らしが11,900円であるのに対し、二人暮らしは14,296円です。
このことから、二人で生活することにより生鮮食品を使った料理の割合が増加した結果、外食や調理食品の利用を抑えられ、食費の削減につながったことがわかります。
参考2:総務省統計局e-Stat「家計調査 2023 世帯人員・世帯主の年齢階級別 1世帯当たりの収入と支出(二人以上の世帯)」
食費を節約できない人の特徴
食費は、毎日の生活費の中で大きな割合を占めています。しかし、いくら節約を心がけていても、なかなか難しいと感じている人が少なくありません。ここでは、食費を節約できない人の特徴について詳しく解説していきます。
1.外食が多い

食費を節約できない人の特徴として、外食が多いことが挙げられます。例えば、仕事で疲れている時や忙しい時には、食材を購入し、自宅で調理をする気力が湧かないため、手軽に食事ができる外食を選択しがちです。
外食は時間と手間を節約できる便利な方法ですが、自炊と比べると一回あたりの費用が高くなります。このように、外食を頻繁に利用することで、結果的に食費の支出が大きくなってしまうのです。
2.食材をすぐに使い切ってしまう
食材をすぐに使い切ってしまう人は、その都度買い物に行く必要が出てきます。頻繁にスーパーへ足を運ぶことで、必要以外の商品を目にする機会が増え、セール品や目新しい食材に惹かれて予定外の買い物をしてしまいがちです。
結果として、食費の支出が増えることになり、かえって節約から遠ざかってしまいます。計画的にまとめた買い物ができないことが、食費節約を難しくしているのです。
3.買った食材をダメにしてしまう
買った食材を無駄にしてしまうことも食費を節約できない人によく見られる傾向です。特に安売りの際に必要以上の量を購入してしまい、結果として野菜がしなびたり、肉や魚が傷んでしまったりするケースが多く見られます。また冷蔵庫の整理整頓がおこなわれていないと、傷みやすいものが冷蔵庫の奥に残ってしまい、食材を無駄にしてしまうこともあるでしょう。
こうした食材の廃棄ロスは、一回あたりの損失は小さく感じられますが、毎日の積み重ねによって家計に大きな負担となってしまいます。
4.食材にこだわりがありすぎる
食費をなかなか節約できないという人には、食材へのこだわりが強すぎるという特徴が見られることがあります。
例えば、野菜を買うときは必ず無農薬のものにこだわる、お肉は特別な飼育方法で育てられた銘柄肉しか買わないなど、値段が高い食材ばかりを選んでしまう傾向があるのです。もちろん、健康や安全のために食材を選ぶことは大切ですが、すべての食材にこだわりを持って選ぶと、家計への負担が大きくなってしまいます。
5.嗜好品を買いすぎてしまう
お酒や菓子などといった嗜好品を買いすぎてしまうことも、食費が減らない原因の一つです。特に、飲酒時にさまざまなつまみを食べたり、ティータイムにスイーツを食べたりするなど、日常的に複数の嗜好品を食べる食習慣がある人は、食費が膨らみやすい傾向にあります。
また、毎朝のコンビニコーヒーや夕食後の晩酌など、ちょっとした嗜好品の飲食が日々の生活習慣に定着していると、気付かないうちに家計を大きく圧迫してしまうのです。
食費を節約する方法
家計の中で大きな割合を占める食費の節約は、多くの人が取り組みたいと考えている課題です。ここでは、食費を節約するための具体的な方法を6つ紹介します。
1.自炊をする
自炊は、食費削減のために効果的な手段です。自炊をすれば食材費だけで済むため、外食や惣菜と比べて食費を抑えることができるからです。
また家にある食材を確認してから旬の食材や見切り品を利用して必要な分だけ購入することで、無駄なく節約することができます。
さらに、余った料理も別の料理にリメイクすれば、味のバリエーションを楽しみつつ、廃棄を減らすことができるので節約につながります。
2.1週間の献立を考えておく
1週間分の献立を事前に立てることで、食費を効率的に節約することができます。計画的な献立作りにより、必要な食材を把握してまとめ買いができ、大容量パックなどの割引商品を活用できるためです。また、買い物リストが明確になることで、衝動買いを防ぐことができます。
さらに1週間の献立を決めておけば食材の無駄が減り、節約につながります。例えば、月曜日のハンバーグの余りの肉を火曜日の肉野菜炒めに使用したり、水曜日の肉じゃがの残りを木曜日のオムレツに活用したりすることで、食材を無駄なく使い切ることができるでしょう。このように1週間単位で献立をつくることで、食材の有効活用や外食の削減につなげられるため、食費を抑えることができるのです。
3.1週間・1ヵ月の食費を決めておく
食費を節約するためには、1週間や1ヵ月といった期間での予算を決めておくことが効果的です。事前に予算を設定することで、無計画な食費の使い過ぎを防ぐことができるからです。
例えば、1ヵ月(4週間)の食費を4万円と決めたとします。それを1週間あたり1万円と分割することで、今週はあとどれくらい使えるのか、使いすぎていないかを意識することができます。週の途中で予算オーバーしそうであれば、外食を控えたり、安い食材で代用したりと、柔軟に対応して予算内に収めるようにしましょう。
4.作り置きをする
作り置きは、食費節約に大きく貢献します。食材を一度に使い切ることで無駄がなくなり、結果として食費を抑えることにつながるからです。
特売で安く買ったひき肉を大量に使ってミートソースを作り、冷凍保存しておけば、後日パスタやグラタンに活用できます。作り置きは、調理時間の節約にもなり、忙しい日や自炊する元気がない日でも、温めるだけで簡単に食事を済ませられるメリットもあります。
このように、計画的に作り置きをすることで、無駄な出費を抑えつつ、時間にも余裕を生み出すことができるのです。
5.安いスーパーを利用する
食費を節約するためには、近所のスーパーの特徴をしっかり把握することが重要です。野菜が安い、肉が新鮮で安い、魚が豊富で安いなど、スーパーによって異なる特徴を理解して店を選びましょう。また、地域に根ざした独立系の安売り店のお買い得品やセールも忘れずにチェックすることが大切です。
さらに、加工食品などの場合は、価格が抑えられたプライベートブランド商品の品揃えで店を使い分けることも節約に効果的です。このようにかしこくスーパーを使い分けることで、毎月の食費を大きく節約できます。
6.ポイントやセールを活用する
食費の節約には、決済サービスのポイント還元キャンペーンやスーパーの特売セールをかしこく活用することが効果的です。チラシやアプリで特売情報を事前にチェックして買い物をすることで、通常よりもお得に商品購入やポイントがゲットできます。
また、店舗のポイントカードと組み合わせることで、ポイントの二重取りができる場合は、さらなる節約効果につながります。
食費の節約をする際の注意点やポイント
食費の節約は家計を見直す上で重要なポイントですが、やみくもに節約するだけでは逆効果になることもあります。ここでは、継続的に実践できる食費節約のコツをご紹介します。
1.無理して節約しようとしない
食費を節約することは大切ですが、無理して節約しようとすると逆効果になることがあります。なぜなら、無理な節約は精神的な負担が大きいため、継続することが難しく、反動で衝動買いなどをしてしまう可能性もあるからです。
いきなり高いハードルを設定するのではなく、できる範囲から始め、無理なく継続することが大切です。食費節約は家計安定に大切ですが、ストレスをためない範囲で行いましょう。
2.冷蔵庫・冷凍庫の中身を把握しておく
食費を節約する上で、冷蔵庫・冷凍庫の中身を把握しておくことは非常に重要です。冷蔵庫の中身を知らずに買い物に行くと、すでに家にあるものを重複して購入してしまう可能性があるからです。
例えば、使いかけの玉ねぎや賞味期限間近のヨーグルトなどが冷蔵庫にあるなら、購入は控えて、まず使い切った方が食費を節約できます。また、冷蔵庫に大根やキャベツが余っているなら、豆腐や豚肉などの合わせやすい食材を買うことで、余りものを一掃しながら、無駄なく1食のメニューを作ることもできます。
このように冷蔵庫の中身を把握しておけば、必要なものだけを買うことができ、食材を無駄なく使い切ることができます。日頃から冷蔵庫の中身を把握し、かしこく買い物をする習慣を身につけましょう。
3.簡単なレシピから挑戦する
普段料理を作らない人は、簡単なレシピの料理から挑戦してみましょう。簡単なレシピを選ぶことで、短時間で調理できる上、料理のハードルが下がり、毎日続けやすくなるからです。
例えば、豆腐と卵を使った炒め物や、野菜をさっと炒めただけのシンプルな料理は、短時間で簡単に作ることができます。まずは簡単な料理から始めて、小さな成功体験を積み重ねることで自炊の楽しさを知りましょう。
そして、完璧主義を捨て、無理せず適度に手間を省くことも、自炊を続ける上で重要なポイントです。気負わずに自炊に取り組むことで、結果的に食費節約に繋がります。
4.冷凍食品も活用する
冷凍食品をかしこく活用すれば、手軽に食費を抑えながら、自炊生活を充実させることができます。冷凍食品は長期保存が可能なので、食材を無駄にすることなく使い切ることができるからです。調理の手間も省けるため、忙しい日でも時間をかけずに食事の準備ができます。
冷凍のカット野菜や、冷凍の鶏肉などを活用すれば、簡単に一食分の料理が完成します。素材系の冷凍食品は一般的に価格が安定しているという点も魅力です。普段料理をしない人でも、上手に活用することで、時間とお金を節約しながら、料理が作れるでしょう。
食費以外で節約する方法
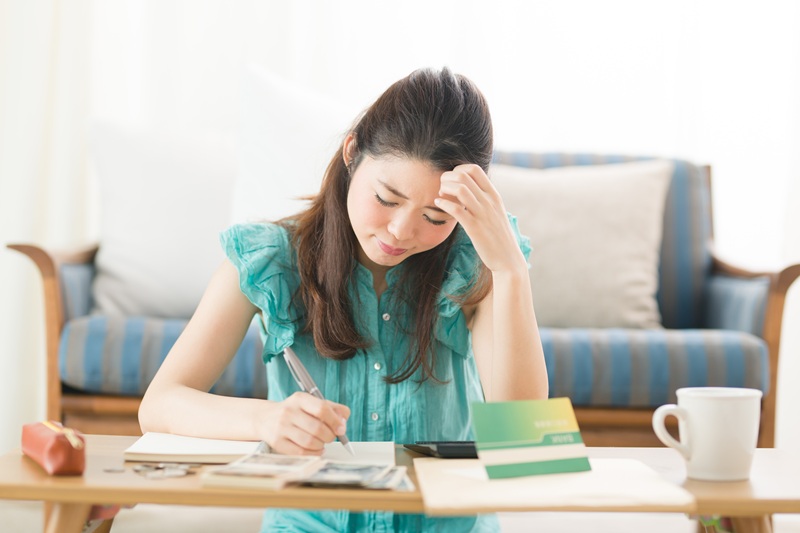
食費の節約は重要ですが、それ以外にも効果的な節約方法はたくさんあります。ここでは、食費以外で節約する4つの方法を紹介します。詳しく見てみましょう。
1.家計簿をつけて収支を把握する
家計簿をつけて家計の収支を把握することは、効果的な節約方法の一つです。家計簿をつけることで、毎月の収入と支出の内訳が明確になり、無駄な出費を見つけやすくなるためです。また、支出を記録する習慣をつけることで、自然と節約への意識が高まります。
毎月の携帯料金や動画配信サービスの支払いを家計簿につけることで、使用頻度の低いサービスに気づき、解約や見直しができます。また、コンビニでの少額購入が積み重なっていることに気づき、代わりにスーパーでのまとめ買いに切り替えるなどの対策を取ることができます。
家計簿の付け方について詳しく知りたい方は「家計簿に必要な項目とは?家計簿をつける際のポイントなども徹底解説!」もご覧ください。
2.先取り貯金をする
先取り貯金をすると、残ったお金で生活することになるので、自然と無駄使いを防ぐことができます。また、毎月決まった金額を貯めるために、お金の使い方を意識するようになり、計画的な支出を促します。
例えば月収25万円の場合、給料日に3万円を貯蓄用口座へ自動振替を設定します。すると、手元に残った22万円の中でやりくりをするため、無駄遣いを防ぐことができます。自動振替にすることで、自分で振り込む手間も省けます。
3.定期的に保険を見直す
保険の定期的な見直しは、食費以外の支出を効果的に抑える手段として有効です。ライフスタイルや経済状況は変化するものであり、それにともない保険の必要性も変わるからです。
結婚や出産、子どもの独立といったライフイベントによって、必要な保障額や種類は変化します。子どもの生活費や教育費が必要なうちは、保護者に万一のことがあると、子どもの生活や進路に影響があるため、必要保障額は厚めにしておきたいものです。しかし、子どもが独立したあとは必要保障額を減らしてもよいでしょう。
また、定年後・子どもの独立後は、死亡保障の必要額が減る一方、病気やケガのリスクが高まります。そのため、死亡保障額を減らして、医療保障を手厚くするなど、保障内容を見直すことで保険料を抑えられる場合があります。
このように保険の見直しは固定費の削減に非常に効果的ですが、必要保障額を減らしすぎると万一のときに保険金が足りなくなってしまうかもしれません。ライフステージや経済状況の変化に合わせて、定期的に保険を見直すようにしましょう。フコク生命のお客さまアドバイザーは、お客さま一人ひとりに最適な商品をご提案するコンサルティングセールスを実施しています。
保険の見直しを検討している方は、ご興味のある商品を選択し、お気軽に「資料請求」をしてみてください。
4.資産運用を考えてみる
新NISAやiDeCoを活用した資産運用も、節約の手段となり得ます。投資による収益や税制優遇制度の利用によって、支出を抑えながら資産を増やすことができるからです。
新NISAを活用することで、1年間に最大で360万円(つみたて投資枠・成長投資枠)まで投資が可能で、その運用益が非課税となります。[参考3]新NISAは比較的短期から中長期の資産形成まで幅広く対応可能です。例えば、5年後の海外旅行資金として100万円、10年後の住宅購入の頭金に300万円などさまざまな目標に合わせた資産運用が可能です。しかも突然お金が必要になった時は、売却できます。
一方、老後の生活資金を貯めたい場合は、iDeCoが有効です。iDeCoは、掛金を積み立てている間も、運用している間も、そして将来お金を受け取る時にも、税金面で大きなメリットがあります。[参考4]iDeCoは原則60歳までは引き出すことができないので、例えば、30年後にゆとりある老後生活を送るための資金として3,000万円を目指すなど老後のまとまった資金を目的に運用するのに最適です。
ただし新NISAやiDeCoを活用しても、投資にはリスクもあるので、目的に合わせて自己責任で最適な投資方法を選ぶようにしましょう。
iDeCoや新NISAについて詳しく知りたい方は、「【新NISA】いよいよ新NISA開始!47都道府県、新NISAにいくら投資する?」や「【iDeCo】47都道府県、iDeCoを活用しているのはどこ?月々の掛金は?」をご覧ください。
どの方法を選ぶにしても、自分に合った節約方法で取り組むことが重要です。節約方法について詳しく知りたい方は「自分に合った節約方法を見つけて節約上手になろう!コツや注意点についても紹介」をご覧ください。
参考3:金融庁「NISAを知る」
参考4:厚生労働省「iDeCoの概要」
まとめ
今回は、食費を節約できない人の特徴や節約する具体的な方法、注意点などについて解説しました。自分の食費を集計し、平均の食費を上回っている場合は、食費の節約を検討したほうが良いでしょう。
外食や調理食品の利用を控えることで食費は抑えられますが、計画的に自炊を進める必要があります。無計画に食費を減らそうとしても、ストレスばかりが溜まって一向に成果が出ない可能性があるからです。
食費を節約する際は、簡単なレシピでの自炊や冷凍食品の活用など、無理せずできることから取り組みましょう。場合によっては、家計簿の見直しや先取り貯金の活用、保険を含めた固定費の見直しなどをおこなって、支出を全体として減らすのも有効です。
※本記事の内容は公開日時点の情報となります。法令や情報などは更新されていることもありますので、最新情報を確かめていただくようお願いいたします
馬場正裕(ばば まさひろ)
FPライター。ファイナンシャル・プランナーとして、各種サイトでマネー記事やコラムの執筆を担当した。消費者金融や外貨預金、家計管理、不動産関連の記事を執筆。FPとしての知識を生かした記事執筆の活動を行っている。2級FP技能士
記事提供元:株式会社デジタルアイデンティティ








