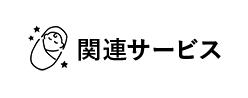期間限定キャンペーン中!
Contents
この記事を読んでいる人におすすめ!

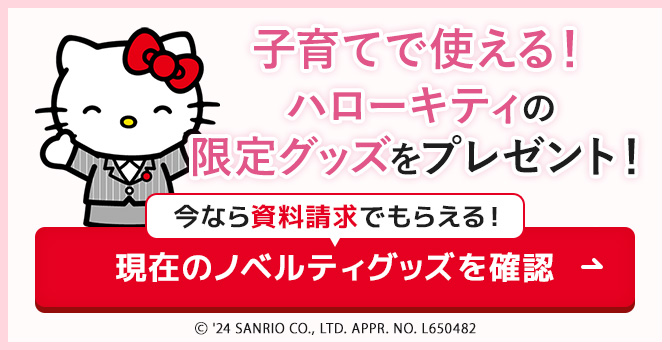
子どもが成長するにつれて「そろそろ子離れしなければ」と思っている方も多いでしょう。子離れできないままでいると、子どもの自立心や主体性が育たず、将来的に社会生活で問題を引き起こす可能性があります。今のうちから、適切な距離感を保ち、子どもの成長を見守る方法を知っておきましょう。
この記事では、子離れの意味や子離れできない親の特徴、子離れする方法、タイミングなどを解説します。
※本記事の内容は公開日時点の情報となります。法令や情報などは更新されていることもありますので、最新情報を確かめていただくようお願いいたします。
子離れとはどういう意味?
「子離れ」とは、親が保護者としての役割を終え、子どもの自主性にまかせられるようになることです。適切な距離感を保ちながら、徐々に手を放すことで子離れできるようになります。子どもが成長とともに自分で考え、判断し、行動する力を身につけられるように見守ることが大切です。
一方で「親離れ」とは、子どもが親に依存した状態から独立していくことを指します。子離れと親離れはつながっており、徐々に子離れすることで、子どもも自然と親離れできるようになります。
子離れできない親の特徴
子離れできない親には共通点があります。次の特徴に心当たりがないか、ご自身の行動を振り返ってみましょう。
1.子どもの成長を受け入れられない
子どもの成長を受け入れられず、いつまでも「自分がいないと何もできない」と思い込んでしまい、子離れできずにいる親がいます。
例えば、子どもが大きくなっても持ち物をチェックしたり、友達関係に過度に口を出したりする行動は、成長を受け入れられていない証拠かもしれません。子どもの年齢に応じた自立を認められず、いつまでも幼い頃と同じような接し方を続けてしまいます。
2.過度に保護・干渉してしまう
「子どものため」という思いから、あらゆることに手を出し、口を出すのも、子離れできない親の特徴です。宿題の内容から友人関係、進路選択など、すべてにおいて親が主導権を握ろうとします。
このような親は、子どもの失敗を極度に恐れ、先回りして問題を解決しようとします。しかし、失敗から学ぶ機会を奪うことで、かえって子どもの成長を妨げていることに気づいていません。
3.自分の理想を押し付けてしまっている
子離れできない親は、無意識のうちに自分の理想や価値観を子どもに押し付けていることがあります。「こうあるべき」「こうしなければならない」という考えから、子ども自身の意思や個性を尊重できません。
例えば、親が叶えられなかった夢を子どもに託したり、特定の職業や進路を強要したりすることが挙げられます。子どもの気持ちを無視して親の期待に応えることを求める傾向があります。
子離れできないデメリット
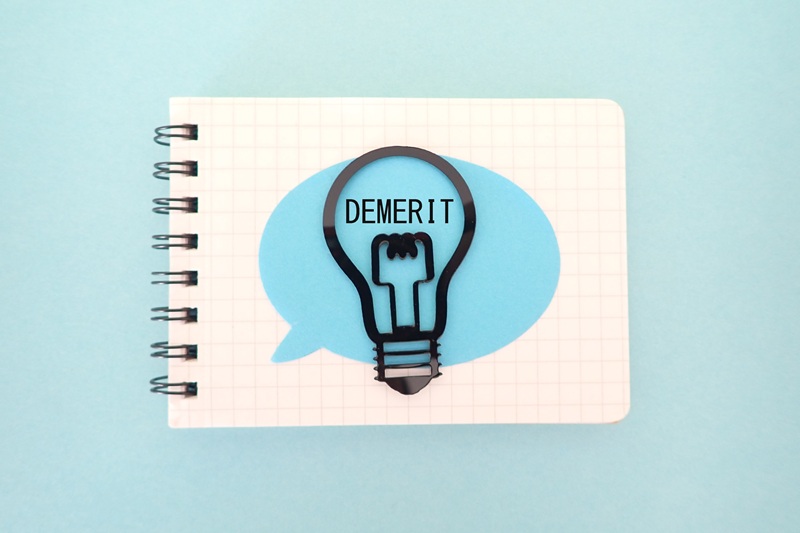
子離れできないことは、子どもの成長に深刻な影響を与えます。親の過度な関与が、子どもの将来にどのような問題を引き起こすのか知っておきましょう。
1.自立心の欠如や主体性が低下する
親が何でも決める環境で育った子どもは、自分で判断したり行動したりする力が育ちません。日常的な選択から重要な決断まで、常に誰かの指示を待つ、受け身の姿勢が身についてしまいます。
このように親が先回りしてすべてを整えると、困難に直面したときの対処法がわからないまま成長してしまいます。子どもは、小さな選択の積み重ねによって、自立心や主体性が育まれますが、その機会を親が奪ってしまうのです。
2.コミュニケーションが苦手になる
過度な干渉や制限を受けると、他者との関わり方を学ぶ機会が減り、コミュニケーションが苦手になってしまいます。親が子どもの人間関係にまで介入すると、子ども自身が対人関係を築く力を身につけられません。
その結果、大人になってからも「自分の考えをうまく伝えられない」「会話が続かない」といったコミュニケーションの悩みを抱えやすくなり、社会生活において困難を感じることが多くなります。
3.自己肯定感が低くなってしまう
常に親の期待に応えようとするあまり、自分の気持ちを言えなくなり、自己肯定感が低くなってしまいます。親のために頑張ることが当たり前となり、自分の本当の願いや感情を押し殺してしまうからです。
こうして自分の意見を言えずに、親の意向に従い続けることで、選択や判断に自信が持てず「親が認めるか」が行動の基準になります。「自分にはできない」「どうせ無理だ」という否定的な思考パターンが定着し、自分の可能性を狭めてしまう可能性があります。
4.責任感が薄れてしまう
親がすべてをやってくれることで、自分の行動に対する責任を感じる機会が少なくなります。失敗しても親が解決してくれる環境で育つと「自分の選択ではない」「言われた通りにしただけ」という考えが定着します。
このように、失敗しても困ったら親が解決してくれる環境では、行動や言動に対して責任を持つ意識が育ちません。このまま責任感が薄い人に育つと、他人のせいにしたり、言い訳をしたりする大人になる可能性があります。
子離れするための方法
一朝一夕にできるものではないものの、次のようなことを意識的に取り組むことで、子離れにつながります。無理のない範囲で、少しずつ実践しましょう。
1.自分の時間を増やす
自分自身に時間を使い、子ども以外に目を向けることが大切です。
子育てに専念してきた親にとって、自分の時間を持つことは罪悪感があるかもしれません。しかし、親自身が成長し続けることは、子どもにとっても良い影響を与えます。例えば、以下の中から、興味を持てることがあれば積極的に挑戦してみてください。
- 習い事を始める
- スポーツジムへ通う
- 資格取得の勉強をする
親が充実した時間を過ごし、一人の人間として人生を楽しむことが、子どもの自立を促します。子どもは親の生き生きとした姿を見ることで、「大人になることは素晴らしい」と感じ、自然と自立への意欲を高めます。また、親が自分の人生に責任を持って取り組む姿勢は、子どもにとって最良の手本となるのです。
2.子どもの意見を聞く・任せてみる
親の意見があっても、まずは子どもがどうしたいのかを聞きましょう。子どもの意見を聞いて任せることで、自立心を育てられます。
聞いた後に全て否定するのではなく、もしダメな場合にはなぜダメなのか、子どもがきちんと納得する理由を説明することが大切です。安全面で問題がなければ、失敗しても、まずはやらせてみる勇気も必要になります。また、先回りせずにやり方を説明するのもおすすめです。
以下のように、日常生活で子どもに任せられることから始めてみてください。
- 料理の手伝い
- 部屋の片づけ
- 買い物
うまくいかなかったとしても、失敗を通して学ぶ経験が、子どもの成長につながります。
3.声の掛け方・話し方を意識する
声の掛け方や話し方を意識することで、子どもとの関係性が変わります。
以下のように、親の考えや決めつけで子どもに伝えていないか、振り返ってみてください。
- 「〜はダメと言ったでしょう」
- 「〜して」
- 「〜はこうすべき」
命令形や断定的な言い方を、提案や質問に変えるのもよいでしょう。例えば「宿題しなさい」ではなく「宿題はどうする?」、「早く寝なさい」を「そろそろ寝る時間だけどどうする?」といった具合です。
子どもが自分で考え、選択の余地を残すことで、主体性が育ちます。日々の声の掛け方や話し方を意識して変えることで、子どもとの関係性が変わっていくでしょう。
4.夫婦で子育てについて話し合う
パートナーと話し合い、それぞれの子育ての考え方や、今後について意見を交換してみましょう。パートナーとの関係性や子育てがうまくいっていないことで、無意識に子どもに依存している可能性があるからです。
夫婦で協力し合えば、どちらか一方が過度に子どもに執着することを防げます。また、両親が協力する姿を見ることで、安心して自立への道を歩めるようになるでしょう。定期的に夫婦で話し合う時間を設け、子育ての方向性を確認することをおすすめします。
子離れのタイミングはいつ?

子離れのタイミングは、子どもの成長段階や性格、生活環境によって異なります。「〇歳になったら子離れする」という決まったタイミングはなく、子ども一人ひとりの成長に合わせましょう。
また、いきなり子離れするのではなく、段階的に進めるのが大切です。急激に変化すると、親子ともにストレスになり、かえって関係を悪化させる可能性があります。
例えば、小学校に入ると自分でできることが増え、考えて行動できるようになります。先回りして何でもすることをやめて、子どもの話を聞き、できることは本人にやってもらうとよいでしょう。朝の支度や持ち物の管理など、できることから少しずつ子どもに任せます。最初は時間がかかったり、忘れ物をしたりするかもしれません。しかし、その経験を通じて子どもは成長していきます。
子離れの時期は、明確に「このタイミングで」と決める必要はなく、周りとの関わりが増え、家族との関係が変化していく中で、自然と子離れをしていくものだと考えましょう。子どもの様子を観察しながら、その子に合ったペースで進めるのが子離れを進めるうえで重要です。
子離れする際のポイントや注意点
子離れは子どもの健全な成長と自立のために必要不可欠なプロセスです。適切なポイントや注意点を理解することで、親子双方にとってスムーズな子離れを実現できます。次に紹介するポイントを意識しながら、焦らず段階的に子離れを進めていきましょう。
1.理想を押し付けていないか見直す
気づかない間に自分の理想を押し付けていないか、振り返りましょう。無意識のうちにおこなっているケースが多いため、自分の言動や態度を見直すことがポイントです。
「良い成績を取ってほしい」「スポーツで活躍してほしい」「優しい子でいてほしい」など、親なら誰しも子どもに対する期待を持っています。しかし、その期待が、子どもの個性や意思を無視したものになっていないか、振り返ってみてください。
日々、子どもとの会話を思い返し「~すべき」「~でなければならない」といった言葉を無意識に使っていないか確認するとよいでしょう。
2.失敗を認め成功は褒める
子どもが失敗したときは認め、成功したときには褒めることが大切です。失敗した際は、責めるのではなく認めることで、子どもは安心して挑戦できるでしょう。
「失敗は成功のもと」という言葉があるように、失敗から学べることはたくさんあります。失敗したときこそ「よく挑戦したね」と努力を認め「次はどうしたらいいと思う?」と一緒に考える姿勢を示してください。
成功した際の「よくできたね」「頑張ったね」という言葉は、子どもの自信につながります。また、成功の結果だけにとらわれずに、そこまでのプロセスもしっかり見逃さず、何が良かったのかを具体的に褒めてあげましょう。
3.見守る姿勢が大事
子どもを信じて見守る姿勢が大切です。手を出したくなる気持ちを我慢し、自分の力で乗り越えるのを待ちましょう。
見守るとは、子どもの様子に注意を払いながら、必要なときにはサポートできる準備をしておくことです。「困ったときはいつでも相談してね」と伝えておくことで、子どもは安心して挑戦できます。
「あなたならできる」と親が子どもを信じれば、子どもの勇気となり、困難に立ち向かう力が育まれます。見守ることは時に忍耐が必要ですが、子どもの成長につながるでしょう。
まとめ
子どもが成長し、進学や就職、結婚などで自立していく姿を見るのは、親として誇らしい反面、寂しさや不安を感じることも多いでしょう。しかし、子離れは子どもの健全な成長と自立に欠かせません。加えて、親自身が新たな人生のステージを楽しむきっかけになります。
子どもの成長や性格に合わせて、段階的に子離れを始めましょう。少しずつできることから始め、親子がお互いを尊重し合える関係性を築いてください。
※本記事の内容は公開日時点の情報となります。
法令や情報などは更新されていることもありますので、最新情報を確かめていただくようお願いいたします。
高山 さとみ(たかやまさとみ)
金融・不動産専門ライター。法学部を卒業後、大手金融会社でライフプランニングの相談・提案業務に従事。その後、インテリアメーカーで建設現場の部材管理を担当。現在は「読者にわかりやすく伝える」をモットーに、ライター・ディレクターとして活動中。2級FP技能士
記事提供元:株式会社デジタルアイデンティティ