
期間限定キャンペーン中!
Contents
50代の平均年収は、前半で615万円、後半では629万円とピークを迎えます。しかし、この平均値は性別や学歴、働く環境によって大きく異なります。
この記事では、50代の年収データを多角的に分析し、セカンドライフを見据えた生活費の目安や、50代からでも実現可能な年収アップの方法を詳しく解説します。
※本記事の内容は公開日時点の情報となります。法令や情報などは更新されていることもありますので、最新情報を確かめていただくようお願いいたします。
50代の平均年収はいくら?
50代の平均年収の推移を、厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」をもとにみていきましょう。[参考1]
【年齢階層別の平均年収(男女計)】
| 50~54歳 | 55~59歳 | |
| 令和6年 | 約615万円 | 約629万円 |
| 令和5年 | 約599万円 | 約605万円 |
| 令和4年 | 約588万円 | 約590万円 |
| 令和3年 | 約589万円 | 約581万円 |
参考1:厚生労働省「令和6年賃金構造基本統計調査」「令和5年賃金構造基本統計調査」「令和4年賃金構造基本統計調査」「令和3年賃金構造基本統計調査」一般労働者 産業大分類 第1表 年齢階級別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額を元に計算し千円未満を四捨五入したもの
直近の令和6年のデータを見ると、50代の平均年収は600万円を超え、生涯で高い水準に達していることがうかがえます。長年培ってきた経験や専門的なスキルが評価され、部長職をはじめとする組織運営の中核を担う役職に就く人が増えることが影響していると考えられます。一方で、50代後半にかけて役職定年を迎える人も出始め、40代に比べて年収の伸び率が緩やかになるのもこの年代の特徴といえるでしょう。
50代の平均月収と手取りはどれくらい?
年収とあわせて、日々の家計に直結する「月収」と、実際に使える「手取り額」もみてみましょう。50代の平均月収は以下のようになっています。
【50代の平均月収】
| 年齢 | 平均月収 |
| 50~54歳 | 約41万円 |
| 55~59歳 | 約42万円 |
この月収の全額が、そのまま銀行口座に振り込まれるわけではありません。給与からは所得税や住民税、社会保険料などが天引きされます。一般的に、最終的な手取り額は、月収のおよそ75%~85%になるといわれています。この目安にもとづいて50代の手取り額を試算すると、以下のようになります。[参考1]
| 年齢 | 手取り月収 |
| 50~54歳 | 約31万円〜約35万円 |
| 55~59歳 | 約32万円〜約36万円 |
50代になると、子どもの独立によって扶養控除が適用されなくなり、手取り額が想定より減るケースも考えられます。
生活設計をより具体的にするためには、この手取り額からどれくらい貯蓄できるかを考えることも重要です。50代の平均貯蓄額や具体的な貯蓄方法については、「50代の平均貯蓄額はどれくらい?今後必要となる費用や貯蓄方法について解説」で詳しく解説しています。
【カテゴリ別】50代の平均年収について
これまで50代全体の平均を見てきましたが、実際の年収は個人の状況によって大きく異なります。ここからはカテゴリ別に、50代の平均年収の具体的な実態を詳しくみていきましょう。
1.男女別の平均年収
50代は、男女間の年収差が大きく、これまでのキャリアの歩み方の違いが年収に最も大きく反映される年代といえます。[参考2]
【男女別平均年収】
| 男 | 女 | |
| 50~54歳 | 約704万円 | 約458万円 |
| 55~59歳 | 約724万円 | 約451万円 |
参考2:厚生労働省「令和6年賃金構造基本統計調査」産業大分類 第1表 年齢階級別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額
男性の平均年収は50代を通じて上昇を続ける一方、女性の平均年収は50代後半でわずかに減少しているのが特徴的です。この結果、男女間の差額は50代後半に約273万円へと拡大します。
50代の男性は管理職などの責任ある立場でキャリアのピークを迎える人が多いでしょう。対して女性の年収が横ばいから微減に転じる背景には、子育てが一段落する一方で、50代後半にかけて親の介護に直面する年代でもあり、働き方を変えざるを得ないという事情が含まれているのかもしれません。
2.学歴別の平均年収
社会人になって約30年が経過する50代は、これまでのキャリアの歩み方が年収という形で最も明確に現れる年代であり、学歴による差は生涯で最大になります。[参考2]
【学歴別平均年収】
| 高校 | 専門学校 | 高専・短大 | 大学 | 大学院 | ||
| 男女計 | 50~54歳 | 約533万円 | 約557万円 | 約554万円 | 約804万円 | 約1,074万円 |
| 55~59歳 | 約530万円 | 約560万円 | 約562万円 | 約864万円 | 約1,137万円 | |
| 男 | 50~54歳 | 約604万円 | 約623万円 | 約715万円 | 約855万円 | 約1,115万円 |
| 55~59歳 | 約602万円 | 約639万円 | 約753万円 | 約904万円 | 約1,172万円 | |
| 女 | 50~54歳 | 約390万円 | 約476万円 | 約497万円 | 約614万円 | 約859万円 |
| 55~59歳 | 約389万円 | 約487万円 | 約496万円 | 約641万円 | 約901万円 | |
高卒と大学院卒の平均年収を比較すると、50代後半の時点で600万円以上の差が生じています。
また、他の学歴の年収が50代でも上昇する中、高卒の平均年収は50代前半から後半にかけて微減しています。長年続いた右肩上がりのカーブが到達点を迎え、人によっては緩やかな下降が見え始めるのです。この背景には、身体的な変化にともなう働き方の変化が影響しているのかもしれません。例えば、製造業の現場や運輸業などで長年、夜勤や交替制勤務を続けてきた方が、50代を機に自らの健康を考慮して日勤中心の無理のない働き方を選択する、といったケースもあるでしょう。
50代の平均年収において、大学院卒は1,000万円の大台を超え、他の学歴とは一線を画す伸びを見せています。特に注目すべきは、他の層が頭打ちを意識し始める50代後半になっても、その上昇カーブが衰えない点です。50代に入ると、大学院卒がマネジメント経験もある高度専門人材という希少性を持ち始めるためだと考えられます。
3.企業規模別の平均年収

50代になると、企業規模による年収の差は生涯を通じて最も大きくなります。[参考2]
【企業規模別平均年収】
| 従業員数 1,000人以上 | 100~999人 | 10~99人 | ||
| 男女計 | 50~54歳 | 約723万円 | 約608万円 | 約498万円 |
| 55~59歳 | 約764万円 | 約615万円 | 約497万円 | |
| 男 | 50~54歳 | 約840万円 | 約696万円 | 約555万円 |
| 55~59歳 | 約885万円 | 約711万円 | 約550万円 | |
| 女 | 50~54歳 | 約512万円 | 約458万円 | 約394万円 |
| 55~59歳 | 約503万円 | 約450万円 | 約399万円 |
50代になると、企業規模による年収格差は40代以前と比べて最も大きくなります。50代後半における大企業と小企業の平均年収の差は、約267万円です。大企業の年収が50代後半にかけても力強く伸び続ける一方で(女性は微減)、中小企業では頭打ち、あるいは微減する傾向が見て取れます。
4.業界別の平均年収
50代になると、業界ごとの年収差がより顕著に現れます。[参考2]
【業種別平均年収】
| 男女計 | 男 | 女 | ||||
| 50~54歳 | 55~59歳 | 50~54歳 | 55~59歳 | 50~54歳 | 55~59歳 | |
| 電気・ガス・ 熱供給・水道業 | 約937万円 | 約937万円 | 約972万円 | 約971万円 | 約683万円 | 約690万円 |
| 情報通信業 | 約808万円 | 約877万円 | 約845万円 | 約912万円 | 約681万円 | 約728万円 |
| 学術研究、専門・技術サービス業 | 約796万円 | 約827万円 | 約879万円 | 約900万円 | 約580万円 | 約591万円 |
| 金融業、保険業 | 約820万円 | 約765万円 | 約1,105万円 | 約977万円 | 約572万円 | 約548万円 |
| 教育、学習支援業 | 約711万円 | 約759万円 | 約832万円 | 約869万円 | 約611万円 | 約622万円 |
| 不動産業、物品賃貸業 | 約695万円 | 約720万円 | 約802万円 | 約860万円 | 約507万円 | 約468万円 |
| 鉱業、採石業、砂利採取業 | 約722万円 | 約667万円 | 約757万円 | 約697万円 | 約508万円 | 約494万円 |
| 建設業 | 約668万円 | 約694万円 | 約701万円 | 約721万円 | 約480万円 | 約492万円 |
| 卸売業、小売業 | 約662万円 | 約679万円 | 約766万円 | 約806万円 | 約442万円 | 約423万円 |
| 製造業 | 約630万円 | 約652万円 | 約703万円 | 約729万円 | 約424万円 | 約402万円 |
| 複合サービス事業 | 約605万円 | 約618万円 | 約675万円 | 約699万円 | 約455万円 | 約428万円 |
| 運輸業、郵便業 | 約552万円 | 約547万円 | 約570万円 | 約564万円 | 約465万円 | 約443万円 |
| 医療、福祉 | 約499万円 | 約505万円 | 約640万円 | 約700万円 | 約453万円 | 約452万円 |
| サービス業 (他に分類されないもの) | 約477万円 | 約479万円 | 約550万円 | 約533万円 | 約364万円 | 約378万円 |
| 生活関連サービス業、娯楽業 | 約467万円 | 約465万円 | 約554万円 | 約550万円 | 約364万円 | 約356万円 |
| 宿泊業、飲食サービス業 | 約453万円 | 約421万円 | 約529万円 | 約498万円 | 約349万円 | 約332万円 |
50代後半の平均年収は、トップの「電気・ガス・水道業」が約937万円であるのに対し、「宿泊・飲食サービス業」は約421万円と、その差は500万円以上に達します。公共性が高いインフラ業界や教育関連の業界は、景気に左右されにくい傾向があるのに加え、年功序列型のため、50代後半でも年収は安定的に上昇し続けるのが特徴です。一方、「運輸業」「宿泊業・飲食サービス業」「生活関連サービス業」など、労働集約型で競争の激しい業界では、体力的な負担の少ない業務へシフトすることなどが影響し、年収が伸び悩む傾向がみられます。
こうした中で、今までトップクラスの年収を誇ってきた「金融・保険業」の男性の平均年収は、50代前半の約1,105万円をピークに、後半には約977万円へと、128万円も急落します。これは、伝統的な金融機関に多い役職定年制度の影響と考えられます。55歳前後で支店長などの役職を離れ、年収が大きく変動する、50代ならではのキャリアの転換点です。
その一方で、「情報通信業」や「学術研究・専門サービス業」は、50代後半でも年収が伸び続けています。これらの業界は成果主義が浸透しており、年齢よりもスキルや実績が評価されやすい傾向にあります。特にIT人材は、企業のDX化を背景に50代でも需要が高く、経験豊富なベテランがむしろ重宝されるフェーズに入っていると考えられます。
5.雇用形態別の平均年収
雇用形態の違いは、50代の年収に非常に大きな差となって現れます。[参考2]
【雇用形態、性別平均年収】
| 性別 | 雇用形態 | 50~54歳 | 55~59歳 |
| 男女計 | 正社員・正職員 | 約662万円 | 約684万円 |
| 正社員・正職員以外 | 約302万円 | 約311万円 | |
| 男 | 正社員・正職員 | 約726万円 | 約754万円 |
| 正社員・正職員以外 | 約349万円 | 約371万円 | |
| 女 | 正社員・正職員 | 約519万円 | 約517万円 |
| 正社員・正職員以外 | 約283万円 | 約281万円 |
50代後半のデータを見ると、正社員の平均年収が約684万円であるのに対し、非正規社員は約311万円と、その差は2倍以上にもなります。正社員は、この年代で部長職や役員といった経営層に近いポジションに就き、高い賞与や手当を得て年収をさらに伸ばす方もいる一方、非正規社員は昇給や賞与の機会が限定的で、年数を重ねても収入増に結びつきにくい構造になっていることが要因の一つと考えられます。
6.地域別の平均年収
住む場所が年収に与える影響は、50代になると最も大きなものとなります。特に、東京一極集中の構図はより鮮明になります。[参考3]
【都道府県別平均年収(男女計)】
| 順位 | 地域 | 50代平均 | 50~54歳 | 55~59歳 |
| 1 | 東京 | 約811万円 | 約789万円 | 約832万円 |
| 2 | 神奈川 | 約675万円 | 約661万円 | 約689万円 |
| 3 | 愛知 | 約652万円 | 約638万円 | 約666万円 |
| 4 | 大阪 | 約644万円 | 約638万円 | 約651万円 |
| 5 | 滋賀 | 約610万円 | 約598万円 | 約622万円 |
参考3:厚生労働省「令和6年賃金構造基本統計調査」都道府県別第1表 都道府県、年齢階級別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額
50代後半の東京の平均年収は約832万円と、2位の神奈川に約140万円以上の差をつけており、その強さが際立ちます。この背景には、多くの企業で役員や本部長といった経営・意思決定層のポストが東京本社に集中していることが挙げられます。これらのポストの存在が、東京の平均年収を強力に押し上げているのでしょう。
そうした中で注目されるのが、5位の滋賀県です。実は滋賀県には、世界的な競争力を持つ電子部品や素材、機械メーカーなどの大規模な工場や研究所が数多く立地しています。これは、京都や大阪、名古屋といった大都市圏への交通の便が良いことに加え、琵琶湖がもたらす豊富な工業用水に恵まれていることなどが挙げられます。50代になると、そうした企業の工場や研究所を統括する工場長や開発責任者といった、責任の重い最終ポストに就く人が出てきます。こうした現場のトップの存在が、県全体の平均年収を引き上げていると考えられます。
【家族構成別】50代の生活費の目安
50代はキャリアの集大成を迎え、セカンドライフへの準備が始まる大切な時期です。ここでは、3つの家族構成別に、家計調査を参考に50代の生活費の目安をみていきましょう。
完全に合致するデータが無いので、一人暮らしは35~59歳以下の人、二人暮らしは50〜59歳以下の二人以上世帯(子育て世帯、三人以上の世帯も含む)、夫婦と子ども1人の生活費の目安は50〜54歳 の夫婦のみ世帯または夫婦と未婚の子どものいる世帯の支出額平均を、この記事では参考としています。
また、消費支出とは、生活に必要な商品やサービスを買うために使うお金のことです。食費や光熱費、交通費など、日常生活で支払う費用が含まれます。
1.一人暮らしの目安
35〜59歳以下の一人暮らしの消費支出の平均は18万4,750円です。データ上の構成比では目立ちにくいものの、50代になると「保健医療」と「教養娯楽」に対するお金のかけ方が、若い頃とは変わってきます。[参考4]
50代の保健医療費は、病気の治療というよりも、将来の健康を守るための予防としての意味合いが強くなるでしょう。人間ドックで身体の状態を定期的にチェックしたり、健康に良い食品で日々のコンディションを整えたりと、長く元気に活動するための自己投資が、この支出に表れています。
また、教養娯楽サービスもご自身の知的好奇心を満たし、人生を豊かにするための時間へとお金の使い方がシフトしていきます。一人でじっくりと芸術に触れたり、映画や演劇、スポーツ観戦に足を運んだり。そうしたご自身の「好き」「やってみたい」を追求するための支出が、この年代の暮らしに彩りを与えるのでしょう。
こうした点を踏まえると、50代の一人暮らしでは、日々の生活費はもちろん、将来の健康維持や、人生を豊かにするための趣味・学びにかかる費用も見込んだ金額が生活費の目安といえるでしょう。
参考4:総務省「2024年 家計調査(家計収支編)単身世帯 詳細結果表」第2表 男女,年齢階級別1世帯当たり1か月間の収入と支出(単身世帯)
2.二人暮らしの目安
50〜59歳以下の二人以上世帯の消費支出の平均は34万8,025円です。ここから、子どもが独立した後の50代夫婦の生活費を考えると、総世帯と比べて「被服及び履物」と「仕送り金」の割合が特徴的です。
被服及び履物への支出は、これまで子ども優先で後回しにしがちだった自分たちのことにお金をかけられるようになった、精神的なゆとりの表れかもしれません。夫婦の旅行に着ていく、お洒落で機能的な服や、健康のために始めたハイキングに必要な靴を揃えるなど、少し上質で生活を彩るための消費が増えていくのでしょう。
そしてもう一つ、この年代を象徴するのが「仕送り金」です。子どもが大学進学を機に一人暮らしを始め、その家賃や生活費を親が援助している、もしくは親が年金暮らしのために仕送りをしているという状況が考えられます。自分たちの楽しみを取り戻しつつ、巣立っていく子どもや年老いた親への責任も果たしている。この過渡期ならではの支出も、50代の暮らしを考える上で無視できない要素です。
日々の生活費に加え、こうした自分たちへの投資と子どもへの最後の投資、親への援助も考慮に入れておくと、より現実的な生活費の目安がみえてくるでしょう。
参考5:総務省「2023年 家計調査(家計収支編)二人以上の世帯 年報」第3表 世帯人員・世帯主の年齢階級別1世帯当たり1か月間の収入と支出(二人以上の世帯)
3.夫婦と子どもが1人の目安
50〜54歳の夫婦と子どもがいる世帯の消費支出の平均は38万2,760円です。その内訳を見ると、「教育費」の割合が高くなっています。[参考6]
これは、子どもの成長段階が高校生や大学生といった、教育費が最もかかる時期になるためです。高校や大学の授業料、あるいは塾や予備校の費用が、家計に重くのしかかります。私立大学や医歯薬系など、子どもの進路によっては、教育費が家計を圧迫することも少なくありません。まさに、家計は子どもの将来への投資が最優先となっている状況といえるでしょう。
この時期の生活費の目安は、家族の基本的な暮らしを支える費用に、人生で最も大きくなる教育費をしっかりと加味して考える必要があります。
参考6:総務省「2024年 家計調査(家計収支編)二人以上の世帯 詳細結果表」第3-6表 世帯類型別1世帯当たり1か月間の収入と支出
夫婦のみの世帯または夫婦と未婚の子供のいる世帯
50代からでも年収アップは可能?
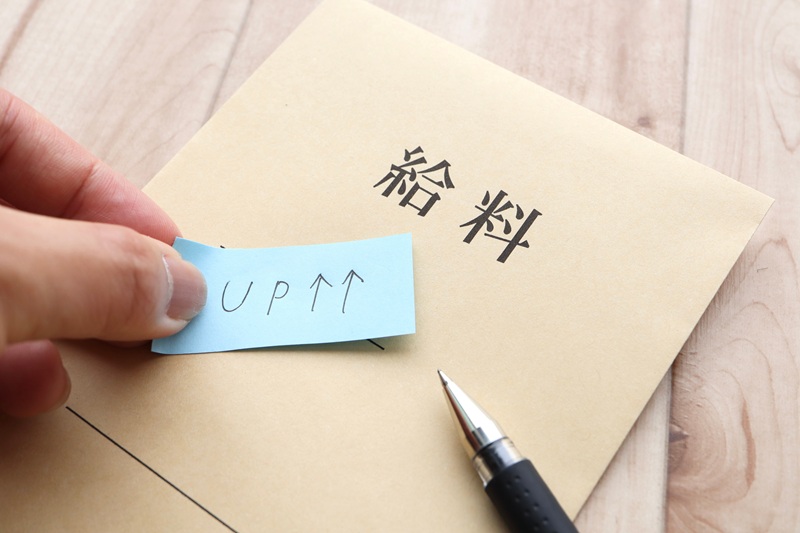
「50代から年収を上げるのは難しいのでは」と感じる方も多いでしょう。確かに厳しい側面もありますが、50代には、これまで培った経験や知識という、他の世代にはない強力な武器があります。ここでは、50代からでもできる年収アップの方法について解説します。
1.副業を検討してみる
50代は、これまで蓄積してきた経験や人脈をいかせる副業を探してみましょう。例えば、長年の実務で培った専門知識を活かし、中小企業やスタートアップの「顧問」や「アドバイザー」として経営課題の相談に乗るような働き方もあります。高い専門性が求められるため、短時間でも高単価を得やすく、体力的な負担も少ないのが魅力です。
また、50代の副業は、定年後を見据えたセカンドキャリアへの助走にもなります。まずはクラウドソーシングサイトなどを活用して、ご自身のスキルが市場でどの程度通用するのかを無理のない範囲で試してみるのもいいでしょう。本業や健康に配慮しながら小さく始めてみると、新たな収入の柱と、これからの人生の生きがいを見つけるきっかけになるかもしれません。
2.思い切って転職をしてみる
50代の転職は簡単ではありませんが、実際に転職して年収をアップできた人も一定数います。未経験分野への挑戦は厳しい側面があるものの、労働人口の減少を背景に、経験豊かなミドル・シニア層を積極的に採用する企業は増える傾向にあります。50代の転職市場で企業が求めているのは、即戦力としての実績です。とくに、マネジメント経験は、業界を問わず高く評価されるでしょう。また、経理や人事、法務といった特定の分野でキャリアを積んできた専門性も強力な武器になります。
成功の鍵は、これまでの経験を具体的に語れるかにあります。単なる経歴としてではなく、「どんな課題を解決し、どんな成果を上げたか」、そして「そのスキルで会社にどう貢献できるか」を明確に伝えられるかが、大切です。
3.独立や起業を考えてみる
会社員としてのキャリアの先に「独立・起業」という道も、50代だからこそ現実味を帯びる選択肢です。
「今から起業なんて」と思うかもしれませんが、50代には若い世代にはない強みがあります。長年の社会人生活で得た業界での評判や人脈は、独立直後の事業を支える大きな基盤となるでしょう。現場で培った深い専門知識は、顧客が抱える本質的な課題を見抜き、的確な解決策を提示する力になります。若い世代に比べて自己資金に余裕があるケースが多く、過度な借入に頼らずリスクをコントロールしながら挑戦できる点も、50代ならではの強みといえるかもしれません。
必ずしも大きな会社を立ち上げる必要はありません。これまでの専門性を活かしたコンサルタントや、一人で始められるフリーランスなど、スモールスタートも立派な独立といえるでしょう。
これからを考えて備えておくことが大事
50代は目前にせまるセカンドライフに向けて、備えを固める時期です。万が一の病気やケガ、あるいは転職や独立にともなう一時的な収入減に備えましょう。まずは当面の生活を支える「生活防衛資金」を準備しておくと安心です。詳しくは「生活防衛資金とは?金額の目安や貯め方のポイントを紹介」で解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。
また、子どもの独立など家族構成の変化は、保険を見直すのに絶好のタイミングです。現状に最適化した保障にすることで、将来への備えを確かなものにしつつ、月々の固定費を削減できる可能性もあります。保険見直しについては、「保険を、定期的に見直していますか?」や「商品一覧」を参考にしてみてください。
まとめ
この記事では、50代の平均年収について、さまざまな角度から詳しくみてきました。50代後半の平均年収は629万円とキャリアのピークを迎えますが、これはあくまで全体の平均値です。実際には、性別や学歴、所属する企業や業界によって、その状況は大きく異なります。これまで積み上げてきたキャリアを土台に、自分にとって本当に大切な働き方や生活のあり方を見つめ直すタイミングかもしれません。平均年収という目安にとらわれすぎず、自身の強みや価値観に合った選択をしていくことが、これからの人生をより充実させるでしょう。
※本記事の内容は公開日時点の情報となります。法令や情報などは更新されていることもありますので、最新情報を確かめていただくようお願いいたします。
佐藤 静香(さとう しずか)
FPライター。損害保険会社に20年勤務後、Webライターとして活動中。保険会社での経験とFPとしての専門知識、また子育て中の母である目線を活かし、難しいお金の話を分かりやすく解説することを得意としている。金融系メディアを中心に、保険、資産形成、家計管理などの記事執筆を担当。2級FP技能士
記事提供元:株式会社デジタルアイデンティティ








