
期間限定キャンペーン中!
人生100年時代と言われる今、50代はまだまだ現役世代。仕事や子育てに一段落ついた今だからこそ、新たなスキルアップやキャリアチェンジなど、さまざまな目的で資格取得を目指す方も多いのではないでしょうか。
本記事では、50代からでも始められるおすすめの資格はもちろん、資格選びのポイント、資格取得までのコツや注意点を解説し、資格取得を成功に導くためのサポートをします。
※本記事の内容は公開日時点の情報となります。法令や情報などは更新されていることもありますので、最新情報を確かめていただくようお願いいたします。
50代で資格を取るメリット
50代は、これまでの経験やスキルを活かしながら新たな挑戦ができる世代です。中でも資格取得は、自分の強みを再発見し、人生の選択肢を広げる手段として注目されています。ここでは50代で資格を取得するメリットについて解説します。
1.視野や人脈が広がる
50代で資格取得に挑戦することで、これまで接点のなかった業界や分野への理解が深まり、視野が大きく広がります。さらに学習を通じてオンライン講座や勉強会に参加する機会が増え、同じ目標をもつ仲間との交流も生まれ、人脈の構築が期待できます。
2.自分に自信が持てる
50代で新たな資格を取得することは、自分自身の可能性を再認識する良い機会です。これまでの経験に加えて資格を取得することで、知識やスキルを習得でき、自分自身の新しい強みが生まれます。まだまだやれるという実感が得られ、自信にもつながるでしょう。
3.人生のやりがいや楽しみが増える
資格を取得することは、人生のやりがいや楽しみが増えるでしょう。子育てや仕事に一区切りついた50代だからこそ、自分の時間を活かし、学ぶ楽しさを再発見できます。また、趣味や興味から始めた資格勉強が、副業や地域活動につながるケースも多く、生活の充実度や経済的なメリットも見込まれるでしょう。
4.転職する際にアピールができる
50代での資格取得は、転職する際のアピールポイントとして有効です。
50代での転職は決して簡単ではありません。しかし、資格を取得していることで明確なスキルや専門性を示すことができ、企業へのアピール材料となります。特に今までのキャリアと関連性のある資格であれば、知識と経験の両立が評価され、中小企業や専門職などで、即戦力としての評価が得やすくなります。
また、50代になってもあきらめず資格取得をするチャレンジ精神がポジティブな印象を与え、年齢のハンデを乗り越える強力な武器になるでしょう。
5.給与アップに繋げられる
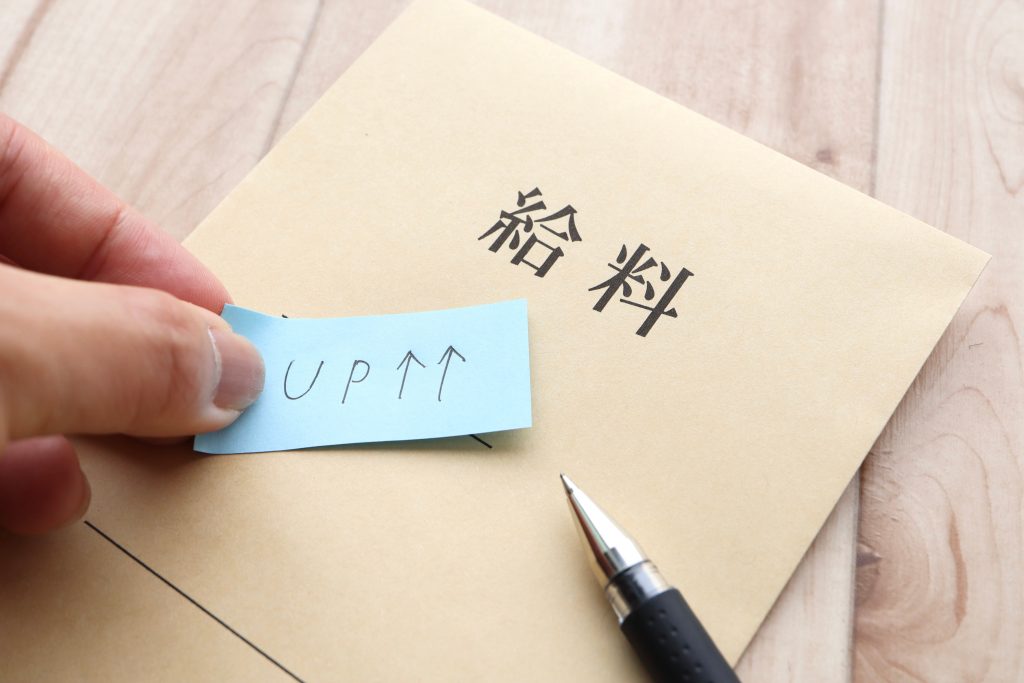
資格を取得することで給与アップが期待できる点も挙げられます。
特に中小企業診断士や行政書士といった、いわゆる「士業」資格を取得すれば、会社によっては資格手当の支給や昇給対象となる場合もあります。また、副業や独立といった選択肢も増えることが見込まれます。資格取得は、自分自身の今後の視野が広がり、ステップアップにもつながるでしょう。
50代におすすめの資格10選
以下では、50代におすすめの資格を10個紹介します。
それぞれの資格の特徴や金額、難易度などを紹介するので、資格取得の参考にしてください。
1.TOEIC
TOEICは、Test of English for International Communicationの略で、実用的なビジネス英語力を測るテストです。多くの企業や団体で評価されており、年齢に関係なく挑戦できる点が魅力です。
観光業界や旅行業界においても英語力が不可欠であるので、スコア次第では50代であっても、新たな分野への道が開ける可能性があります。[参考1]
| 難易度・平均スコア | 難易度(目安):★~★★★★★ ※目標点数で難易度は変動 (あくまで目安ですが、英検4級:260点~、英検3級:291点~、英検準2級:450点~、英検2級:550点~、英検準1級:740点~、英検1級:870点~くらいです) 平均スコア:612点(2023年度) |
| 資格の種類 | 民間資格 |
| 受験資格 | 制限なし |
| 試験形式 | マークシート方式(リスニング100問+リーディング100問) 10点~990点、5点刻みのスコアで評価 |
| 試験時間 | リスニング約45分とリーディング75分 |
| 試験頻度 | 年10回以上(全国主要都市で開催) |
| 受験料 | 7,810円 |
参考1:一般財団法人 国際ビジネスコミュニケーション協会「TOEIC® Listening & Reading Test」
2.行政書士
行政書士は、官公署に提出する各種書類の作成や手続きの代理、相談業務などをおこなう法律系の国家資格です。学歴や年齢に関係なく受験でき、合格すれば即ビジネスチャンスにつながります。開業すれば「街の法律家」として独立も可能で、相続・遺言・契約書作成など幅広い業務に携わることが可能です。
50代からの挑戦者も多く、人生経験や社会人としての信用が強みとして活かせる点も魅力です。[参考2]
| 難易度・合格率 | 難易度:★★★★★ 合格率:12.9%(2024年度) |
| 資格の種類 | 国家資格 |
| 受験資格 | 制限なし |
| 試験形式 | 行政書士の業務に関し必要な法令等(択一・記述) 行政書士の業務に関し必要な基礎知識(択一) |
| 試験時間 | 約180分 |
| 試験頻度 | 年1回 |
| 受験料 | 10,400円 |
参考2:一般財団法人 行政書士試験研究センター「令和7年度行政書士試験のご案内」
3.ファイナンシャルプランナー(FP)
ファイナンシャルプランナーは、税金や保険、年金などの幅広い知識と視野をもち、ライフプランの設計をおこなうお金の専門家です。
特に50代は、相続や不動産など、今後起こるかもしれないイベントのお金の勉強になるので、有効な資格取得となるでしょう。[参考3] 主催は日本FP協会と金融財政事情研究会(きんざい)の2団体があり、試験範囲が異なります。どちらを受験しても難易度はあまり変わりませんが、試験範囲を確認しておくようにしましょう。
| 主催者 | 日本FP協会 | 金融財政事情研究会(きんざい) |
| 難易度・合格率 | 難易度:★★~★★★★ 合格率: 1級 82.4%(実技) 2級 47.1%(学科)56.5%(実技) 3級 86.2%(学科)85.8%(実技) (1級・2級:2024年9月実施分、 3級:2024年4月~2024年9月実施分) | 難易度:★★~★★★★ 合格率: 1級 16.95%(学科) 2級 29.70%(学科)45.17%(実技) 3級 52.55%(学科)47.74%(実技) (2024年5月26日実施分) |
| 資格の種類 | 国家検定 | |
| 受験資格 | 1級:日本FP協会のCFP認定者、きんざい1級技能検定学科試験の一部合格者など 2級:3級FP技能検定の合格者など 3級:FP業務に従事している者または従事しようとしている者 | 1級(学科):2級合格者で、FP業務に関し1年以上の実務経験を有する者など 1級(実技):1級学科試験の合格者など 2級:3級技能検定の合格者など 3級:FP業務に従事している者または従事しようとしている者 |
| 試験形式 | 1級:筆記(記述式) 2級:CBT(Computer-Based Testing)方式および記述式 3級:CBT方式 | 1級:CBT方式(学科)/面接(実技) 2級・3級:CBT方式 |
| 試験時間 | 1級:120分(実技) 2級:120分(学科)、90分(実技) 3級:90分(学科)、60分(実技) | 1級:300分(学科)、半日(実技) 2級:120分(学科)、90分(実技) 3級:90分(学科)、60分(実技) |
| 試験頻度 | 1級:年1回 2級・3級:通年受付 | 1級:年2回 2級・3級:通年受付 |
| 受験料 | 1級:20,000円(実技) 2級:5,700円(学科)6,000円(実技) 3級:4,000円(学科)4,000円(実技) | 1級:8,900円(学科)28,000円(実技) 2級:5,700円(学科)6,000円(実技) 3級:4,000円(学科)4,000円(実技) |
参考3:日本FP協会「FP技能検定」、一般社団法人 金融財政事情研究会「FP技能検定」
ファイナンシャルプランナーの勉強法について、詳しく知りたい方は、「【合格体験談アリ】ファイナンシャルプランナー3級・2級は独学でも取得できる? | あなたの地域のお金情報 ~よんななライフ~」もご覧ください。
4.社会福祉士
社会福祉士は、福祉の相談援助に関する高度な専門知識・技術を有し、福祉や医療の相談援助の場において重要な役割を担う、社会福祉専門職の国家資格の1つです。ただし、社会福祉士の受験資格には、福祉系大学ルート、短期養成施設ルート、一般養成施設ルートいずれかの学歴と実務経験が必要になります。
社会福祉士は、50代の豊かな知見と人生経験を活かしながら、社会に貢献できる職業です。新たなキャリアを築くうえで、まさに理想的なステージといえるでしょう。[参考4]
| 難易度・合格率 | 難易度:★★★ 合格率:56.3%(2024年度) |
| 資格の種類 | 国家資格 |
| 受験資格 | ・福祉系大学ルート ・短期養成施設ルート ・一般養成施設ルート |
| 試験形式 | 五肢択一を基本とする多肢選択形式 |
| 試験時間 | 225分 |
| 試験頻度 | 年1回 |
| 受験料 | 一般受験者:19,370円 精神保健福祉士と同時受験者:16,840円 科目免除者:16,230円 |
参考4:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「社会福祉士国家試験」
5.中小企業診断士
中小企業診断士は、企業の経営課題を分析し、改善策を提案する専門家で、経営コンサルタント唯一の国家資格です。経営・財務・人事・マーケティングなど幅広い知識が求められ、中小企業を支援する公的機関や金融機関からも信頼されています。
50代の方にとっては、これまでの職務経験を活かしながら再就職や独立、地域貢献を目指せる資格として注目されています。[参考5]
| 難易度・合格率 | 難易度:★★★★★ 合格率:2024年度27.5%(1次試験)、18.7%(2次試験) |
| 資格の種類 | 国家資格 |
| 受験資格 | 制限なし |
| 試験形式 | 1次試験:マークシート方式による多肢選択式 2次試験:記述・口述 |
| 試験時間 | 1次試験:60分および90分(7科目) 2次試験:各80分(4問) |
| 試験頻度 | 年1回 |
| 受験料 | 1次試験:14,500円 2次試験:17,800円 |
参考5:一般社団法人 日本中小企業診断士協会連合会「令和6年度の試験について」「令和7年度の試験について」
6.簿記
簿記は、企業の財務活動を記録・計算・整理して、企業の財政状況を明らかにする技能で、この技能の習熟度を測るのが日商簿記検定です。日商簿記3級は基本的な商業簿記が対象で初心者向き、2級は工業簿記を含む実務対応で経理職志望や管理職の方に人気があります。
学歴・年齢・国籍問わず受験可能で、50代の方は、これまでの経験と組み合わせれば、再就職や副業、企業支援において、会社の数字に強い人材としての価値が高まります。[参考6]
| 難易度・合格率 | 難易度:3級★★、2級★★★★、1級★★★★★ 合格率:3級38.6%(ネット試験)、2級35.7%(ネット試験)、1級15.1%(統一試験)(ネット試験は2024年度、統一試験は2024年11月度) |
| 受験資格 | 制限なし |
| 試験形式 | 3級:筆記による統一試験・ネット試験 2級:筆記による統一試験・ネット試験 1級:筆記による統一試験 |
| 試験時間 | 3級:60分(筆記による統一試験・ネット試験) 2級:90分(筆記による統一試験・ネット試験) 1級:180分(筆記による統一試験) |
| 試験頻度 | 3級・2級:年3回(筆記による統一試験)、随時(ネット試験) 1級:年2回(筆記による統一試験) |
| 受験料 | 3級:3,300円 2級:5,500円 1級:8,800円 ※ネット試験は事務手数料550円 |
参考6:日本商工会議所「簿記」、大阪商工会議所「日商簿記検定」
7.登録販売者
登録販売者は、薬局やドラッグストアで一般用医薬品の販売ができる医薬品販売の専門資格です。試験範囲は医薬品の知識や法規、安全対策が中心です。生活に直結する健康関連の知識が身につき、地域社会や家庭でも役立つ実用性の高い資格といえるでしょう。
学歴・実務経験不要で誰でも受験可能であるため、50代からのキャリアチェンジや副業としても取り組みやすいです。[参考7]
| 難易度・合格率 | 難易度:★★ 合格率:46.7%(2024年度) |
| 受験資格 | 制限なし |
| 試験形式 | マークシート方式 |
| 試験時間 | 240分 |
| 受験料 | 都道府県により異なる (12,800円~18,200円ほど) |
参考7:神奈川県「登録販売者試験(概要)」、関西広域連合「令和7年度 登録販売者試験受験案内」
8.ケアマネジャー(介護支援専門員)
ケアマネジャー(介護支援専門員)は、高齢者や障がいのある方が安心して暮らせるよう、介護サービス計画(ケアプラン)を作成し、関係機関と連携する専門職ですケアマネジャーになるには、福祉・介護の現場で5年以上・900日以上の実務経験が必要で、知識だけでなく実務力も求められます。
50代からでも介護分野で信頼される存在を目指せる資格といえるでしょう。[参考8]
| 難易度・合格率 | 難易度:★★★★ 合格率:32.1%(2024年度) |
| 受験資格 | 介護福祉士・看護師・社会福祉士などの国家資格等に基づく業務や相談援助業務の従事期間が通算5年以上で、従事した日数が900日以上である者 |
| 試験形式 | マークシート方式、60問 |
| 受験時間 | 120分 |
| 受験料 | 都道府県により異なる (7,400円~ 13,600円ほど) |
参考8:社会福祉振興・試験センター「介護支援専門員(試験問題作成)」
9.賃貸不動産経営管理士

賃貸不動産経営管理士は、賃貸住宅の管理に必要な知識や技能、倫理観をもち、適正な管理業務をおこなえる専門家です。
年齢や学歴に制限なく誰でも受験できる点が特徴で、不動産業界で実務に関わる方はもちろん、セカンドキャリアとして、50代の人にも目指しやすい資格です。[参考9]
| 難易度・合格率 | 難易度:★★★ 合格率:24.1%(2024年度) |
| 資格の種類 | 国家資格 |
| 受験資格 | 制限なし |
| 出題形式 | 四肢択一、50問 |
| 受験時間 | 120分 |
| 試験頻度 | 年1回 |
| 受験料 | 12,000円 |
参考9:一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会「令和7年度 賃貸不動産経営管理士試験実施要領(国土交通大臣登録試験) 」
10.宅地建物取引士
宅地建物取引士(宅建士)は、不動産取引における重要な国家資格で、取引の安全を確保するために説明義務や文書交付、契約時の立会いなどを担います。賃貸不動産経営管理士と同様に年齢・学歴に関係なく誰でも受験可能です。資格取得後は、不動産業はもちろん、金融・建築業界などでも求められる専門性の高い資格です。
特に50代は、セカンドキャリアはもちろん、相続・売却・賃貸運用といった場面で自分自身や家族の資産管理にも応用できるのでおすすめの資格です。[参考10]
| 難易度・合格率 | 難易度:★★★★ 合格率:18.6%(2024年度) |
| 資格の種類 | 国家資格 |
| 受験資格 | 制限なし |
| 出題形式 | 四肢択一、50問 |
| 受験時間 | 120分 |
| 試験頻度 | 年1回 |
| 受験料 | 8,200円 |
参考10:一般財団法人 不動産適正取引推進機構「宅建試験の概要」
50代からの資格取得、どう選べばいい?
おすすめの資格を紹介しましたが、どのように選べばいいのか迷われる方もいるかもしれません。ここでは、選び方の例を紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
1.今後やりたいことで選ぶ
資格を選ぶ際には、自分が今後やってみたいことで選ぶことをおすすめします。
20-40代の時には、仕事や子育てなどで忙しく、やりたくてもできなかったことがあるかもしれません。
50代になったら取得したい資格があるのならば、迷わずに打ち込むことをおすすめします。また、今後のライフプランを考え、目標となるものがあれば、関連した資格を取得するのがいいでしょう。
2.これまでの経験や知識を活かせるかどうかで選ぶ
これまでの職務経験や知識を活かせる資格を選ぶことも、50代からの資格取得がうまくいく秘訣であるといえます。全く新しい分野の資格取得であれば、不安になったり、余計なストレスがかかったりするかもしれません。もともと知見があるジャンルの資格を選択することで、過度なストレスを感じることがなく、スムーズに進めていくことが期待できます。
3.難易度や勉強時間で選ぶ
50代での資格取得では、資格の難易度や必要な勉強時間も重要な検討ポイントです。難関資格に挑戦するには、相応の時間がかかります。場合によっては途中で投げ出してしまう恐れもあるかもしれません。仕事や家事など、資格取得に費やせる時間も限られている場合では、自分のレベルに見合った資格を選択した方がうまくいくケースが多いのでおすすめです。
50代で資格を取得するためのコツや注意点
50代からの資格取得は、これまでの経験を活かせる反面、体力や集中力、時間の制約といった壁にも直面します。ここでは、50代で資格を取得するためのコツや注意点について見ていきましょう。
1.取得までのスケジュールを立てる
取得したい資格が決まれば、まず取得までのスケジュールを立てましょう。50代での資格取得には、無理のないスケジュール管理が欠かせません。家庭や仕事との両立を前提に、月単位や週単位でスケジュールを組み、1日の中で学習に充てられる時間を具体的に把握します。無理のないスケジュールを立てることが、資格取得の第一歩となるでしょう。
2.仕事に影響が出ない範囲で進める
資格取得は将来への投資ですが、現在の仕事や生活を犠牲にしないことが前提とすべきでしょう。50代は管理職や責任ある立場にある人も多く、無理な学習計画は心身の負担につながりかねません。仕事に支障をきたさないよう、例えば通勤時間を活用した音声の学習や、週末のまとまった時間を使うなど、生活の中に自然と学習を組み込む工夫が必要です。
3.自分に合った勉強法を見つける
自分に合った勉強法を見つけることも、50代で資格を取得するためには重要です。
50代での資格取得は、若い頃と同じやり方が必ずしも適しているとは限りません。また、他の人がおこなっている勉強法が、自分自身に当てはまる保証もありません。共通の目標をもった人と一緒に勉強したり、あるいは独学でなく通信講座を利用したりするなど、自分に合った勉強法を見つけることが重要です。
まとめ
資格の取得は、自分自身のキャリアアップや社会貢献など、メリットが多くあります。一方で、自分自身に適さない資格を選択すると、途中で挫折する恐れがあるので注意が必要です。
今後やりたいことや、今までの経験が生かせる資格を選ぶことで、勉強がスムーズにはかどり、50代からの資格取得が有意義なものとなるでしょう。
※本記事の内容は公開日時点の情報となります。法令や情報などは更新されていることもありますので、最新情報を確かめていただくようお願いいたします。
宮本 建一(みやもと けんいち)
マネーライター。銀行・消費者金融・信用組合の勤務を経て独立。融資経験・FPの知見を生かし、各種サイトで主に資金調達、不動産関連記事の執筆を行う。金融専門誌への寄稿、金融機関行職員向けの通信講座教材執筆経験あり。2級ファイナンシャルプランニング技能士、AFP
記事提供元:株式会社デジタルアイデンティティ








