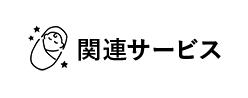期間限定キャンペーン中!
Contents
この記事を読んでいる人におすすめ!

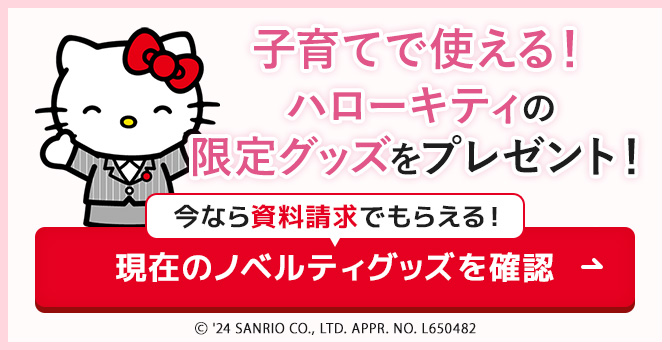
赤ちゃんの1歳のお祝い行事として古くからおこなわれてきた「一升餅」。名前は聞いたことがあっても、実は内容はよくわからないという方も多いかもしれません。
この記事では、そんな「一升餅」について、由来や意味、準備するもの、伝統的なやり方、注意点などを詳しく解説します。
※本記事の内容は公開日時点の情報となります。法令や情報などは更新されていることもありますので、最新情報を確かめていただくようお願いいたします。
一升餅とは?
一升餅は「赤ちゃんが1歳になったお祝いに、約1.8kgのお餅を背負わせる」という日本の伝統行事です。まずは、一升餅という行事の由来や目的をご紹介します。
1. 一升餅の由来
一升餅という風習は、昔、乳幼児の死亡率が高かったことから、1歳を特別な節目として盛大に祝うために始まったものとされています。稲作文化に根ざした日本では、お米から作られたお餅は神聖なものとされ、古くからお祝い事に欠かせない存在でした。一升餅の「一升」は「一生」を、丸い形は「円満」「健康」を、お餅はよく延びることから「長寿」を象徴しています。
「誕生餅」とも呼ばれるこの行事には、このような日本の文化と歴史が背景にあるのです。
2. なぜ一升餅をやるの?
一升餅の行事は、赤ちゃんの初めての誕生日を祝う大切な行事です。背負い餅を背負ったり、踏んだりという行為は、困難に立ち向かう力や、将来の成功を祈る意味も持ち合わせています。家族や周囲の人が集まり、一升餅の行事を見守ることで、赤ちゃんの健やかな成長を願い、喜び合う大切な機会としての意義もあるのです。
このような背景で一升餅は、親子の愛情や家族の絆を深める重要な文化的イベントの1つとして位置づけられています。
一升餅をやる前の準備

一升餅の行事は古くから存在しますが、現代では形式に則っておこなっても、パンやバームクーヘンを使用するなどご家庭の好みや事情に合わせてアレンジしてもよいでしょう。
こちらでは、一升餅をおこなう前の準備品や、しておきたいことをご紹介します。
1. 一升餅
一升餅は、自分で作ることも可能ですが、和菓子屋さんやベビー用品店、インターネット通販などで手軽に購入することもできます。最近では、伝統的な丸いお餅だけでなく、参加者に分けることができる「小分けタイプ」もあります。またお餅の代わりとして「一升パン」や「一升バームクーヘン」なども人気を集めています。こちらは、食パンやフランスパン、バームクーヘンの生地を2kg使い焼き上げたものです。名入れサービス付きの場合もありますので、特別な思い出を残す手助けにもなるでしょう。
2. 風呂敷・リュック
風呂敷やリュックは、一升餅を赤ちゃんに背負わせるために必要なアイテムです。昔ながらのスタイルなら風呂敷です。お餅を包んで斜めがけに背負わせます。また、最近では可愛らしいリュックも人気があります。リュックは赤ちゃんでも背負いやすく、お祝い後も普段使いできる点が魅力です。
伝統的な風呂敷か、実用的なリュックか、自分たちに合う方を選びましょう。
3. 草履・わらじ
一升餅では、草履やわらじを履かせる風習もあります。伝統的なわらじや、現代風にアレンジされた草履など、デザインは豊富です。実際に履かせる場合は、転倒の原因にならないよう、足に合ったサイズを選びましょう。記念写真用の場合は、デザインを重視して、思い出に残る一足を見つけましょう。
4. いつやるのか・誰が参加するのか確認しておく
日程や参加者の確認を早めにしておくことも大切です。一般的には赤ちゃんの1歳の誕生日に合わせておこないますが、平日か休日か、自宅か祖父母宅かレストランかなど候補をいくつか用意しておきましょう。特に、小分けタイプの一升餅を準備する場合には、参加人数を把握しておく必要があります。
また、当日の思い出を残すためのビデオやカメラの準備もお忘れなく。余裕を持った準備で、思い出に残る一升餅の記念日(1歳の誕生日)をお祝いしましょう。
一升餅のやり方や流れについて
一升餅にはいくつかの方法があります。今回は、一般的な方法として知られる「背負い餅」と「踏み餅」という2つのやり方をご紹介します。
1. 一升餅を背負うやり方
こちらは「背負い餅」と呼ばれる、赤ちゃんに一升餅を背負わせるやり方です。
まず、一升の餅を風呂敷の真ん中に置き、対角線上の角を合わせてきれいに包みます。次に、残りの角をそれぞれくるくると巻きつけて、ひも状にします。赤ちゃんに斜めに背負わせたら、ひも状の部分を前で結びましょう。
ずっしり重い一升餅を背負った赤ちゃんは、立ち上がろうとしたり、転んでしまったり、泣いてしまったりなど、反応はさまざまです。なかには、ヨチヨチと歩き出す子も。我が子が一生分の重みを感じ、どんな反応を見せるのか、ご家族みんなで温かく見守りましょう。
2. 一升餅を踏むやり方
一升餅といえば、背負うイメージが強いですが、地域によっては赤ちゃんに一升餅を踏ませるやり方もあります。こちらは「踏み餅」とも呼ばれます。しっかりと立つことで「地に足をつけて力強く歩んでいけるように」という願いが込められています。ただし、まだ子どもは立つことがおぼつかない場合もあるので、つかまり立ちや大人が支えてあげる形で、安全におこないましょう。
踏み餅では、草履やわらじを履かせたり、または素足で、ザルに入れたお餅を赤ちゃんに踏ませるのが基本です。草履やわらじの鼻緒に足の指を通すのが難しい場合は、鼻緒をグッと引っ張りスペースを確保すれば、足の親指と人差し指の間に鼻緒が挟まりやすくなります。
地域によってやり方は異なる?
一升餅の行事は子どもの健やかな成長を願っておこなわれますが、そのやり方は地域によって実にさまざま。全国的にもっとも一般的なのは、風呂敷で包んだ一升餅を背負わせて歩かせる方法です。
地域別に見ると、東日本では背負わせるやり方が主流となっています。一方、九州地方では、わらじを履かせたり、ザルに入れたりして一升餅を踏ませるやり方が一般的です。福岡では、踏ませた後、背負って歩く習慣も存在します。その他にも、一升餅を抱っこさせたり、早く歩き出した子には家を出ていかないようにわざと転ばせたりと、それぞれ地域ならではの風習が見られます。
このように一升餅の行事は、地域独自の文化を反映しながら、親から子へと愛情と願いが受け継がれていく、大切な伝統行事といえます。計画を立てる前に、両家のご両親に地域のやり方を相談してみるのも良いかもしれません。
一升餅をやる際の注意点

一升餅をおこなう当日は、まだ足元がおぼつかない赤ちゃんにとって、お餅を背負ったり、歩かせたりと慣れないことだらけです。行事を安全に進めていくためにも、ぜひ次の3点には注意しましょう。
1. 風呂敷は首に負担がかからないように注意
一升餅を「背負い餅」でおこなう場合は、餅を入れた風呂敷を斜めがけにすることが大切です。これは、お餅の重さで赤ちゃんの首が締まらないようにするためです。
安全のため、風呂敷は必ず片方の肩から反対側の脇の下へ、斜めがけにして背負わせましょう。
または、赤ちゃんの首への負担を考えて、背負いやすいリュックを準備するのもおすすめです。
2. 無理に立たせたり、歩かせたりしない
満1歳の赤ちゃんにとって、一升餅はかなりの重量です。無理に立たせたり歩かせたりせず、赤ちゃんのペースに合わせましょう。
一升餅の行事では「立った方が縁起が良い」と思われがちですが、実際にはどの行動も縁起が良いとされています。転倒しても縁起が悪いということはありません。重たいお餅の場合は軽くする、大人がサポートするなど配慮して、温かく見守りましょう。
3. スペースを確保しておく
一升餅をおこなう際は、狭い場所だと転倒やケガにつながる可能性がありますので、広々とした安全なスペースを確保しておくことが大切です。赤ちゃんが予想外の動きをすることも考えられますので、滑りやすい床や段差がないかなど、事前に注意しておきましょう。
一升餅と一緒におこなわれる「選び取り」についても知っておこう
一升餅とともにおこなわれることの多い「選び取り」は、赤ちゃんの将来を占う楽しいイベントです。赤ちゃんの前にさまざまな道具やカードを置き、最初に手に取ったもので将来の職業や才能を予想します。並べるアイテムの代表例と意味をご紹介しましょう。
| ふで | 芸術の才能あり、物書き・芸術家になる |
| お金 | お金に困らない、お金持ちになる |
| 箸・スプーン | 食べ物に困らない、料理人に向いている |
| 本・辞書 | 成績優秀になる、学者タイプ |
| そろばん・電卓 | 計算が得意になる、商売上手になる |
| 楽器 | 音楽の才能がある |
| 定規 | 几帳面でしっかり者、設計士になる |
アイテムは好きなものでかまいません。
ぜひ、家にあるものを使って、赤ちゃんの未来を占ってみてください。
まとめ
一升餅は、赤ちゃんの1歳の誕生日を祝う日本の伝統行事です。約1.8kgのお餅を背負わせて、健康や長寿、円満な人生を願います。お餅は風呂敷で包んで赤ちゃんに背負わせる「背負い餅」が主流ですが、「踏み餅」というやり方が一般的な地域もあります。また最近では、お餅の代わりにパンやバームクーヘンなどの代替品も人気です。ご家庭に合ったやり方に必要な準備品を用意しましょう。
当日は、赤ちゃんの安全を最優先に考えることが重要です。無理に立たせたり歩かせたりせず、温かく見守りましょう。未来の職業や才能を占う「選び取り」というイベントをあわせておこなうのもおすすめです。準備をしっかりおこない、ご家族の思い出に残るお祝いの時間を過ごしましょう。
※本記事の内容は公開日時点の情報となります。法令や情報などは更新されていることもありますので、最新情報を確かめていただくようお願いいたします。
是枝花名子(これえだ かなこ)
FPライター。大学卒業後、大手生命保険会社にて法人営業を担当。住宅ローンの繰り上げ返済、子どもの教育資金や老後資金作りを極めるため、改めてFP技能士を取得。専門知識と主婦目線を活かした記事執筆が好評を呼び、現在は主にメガバンク、大手不動産サイト等にて保険・不動産・翻訳ライターとして活動中。2級FP技能士
記事提供元:株式会社デジタルアイデンティティ